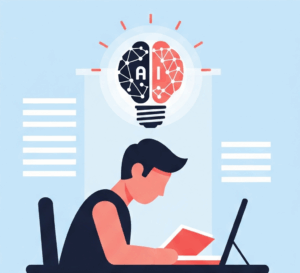
この章は、法律を初めて学ぶ方にとって、法律というものがどういうものなのか、基本的な概念や考え方を理解するための土台となる部分です。
行政書士試験の学習を始めるにあたり、まずは「法とは何か?」という基本的な問いからスタートしましょう。この章では、法律が社会でどのような役割を果たし、私たちの生活や行政活動とどのように関わっているのかを学びます。法律独特の専門用語や概念も多く出てきますが、焦らず一つずつ理解を深めていきましょう。ここでの基礎固めが、今後の憲法や行政法、民法などの学習をスムーズに進めるための大切な一歩となります。
2.1 法とは何か?法律の基本概念
2.1.1 法の意義と役割
私たちは、普段意識せずとも様々な「法」の中で生活しています。では、そもそも「法」とは何でしょうか?
「法」とは、社会の秩序を維持し、人々の争いを解決するために、国家によって強制力をもって適用されるルールのことです。
身近な例を挙げると、信号を守る、お店で代金を払って商品を買う、人を傷つけたら罰せられる、といったルールはすべて「法」に基づいています。
法の主な役割は以下の通りです。
- 社会秩序の維持: 人々が安心して生活できるよう、行動の規範を示し、無用な争いを防ぎます。
- 紛争の解決: 争いが生じた際に、公平な基準に基づいて解決の指針を与えます。
- 個人の権利の保障: 個人の自由や権利を尊重し、不当な侵害から保護します。
- 公共の福祉の実現: 社会全体の利益のために、個人の権利を調整したり、特定の行為を制限したりします。
2.1.2 法の種類と分類
法は、様々な基準で分類されます。主な分類方法を理解することで、それぞれの法律がどのような性格を持っているのかが分かります。
(1) 公法と私法
- 公法(Public Law):国家や公共団体と、国民(個人や法人)との関係を規律する法です。国家権力の行使や、国民の権利義務に関わります。
- 例: 憲法、行政法、刑法、訴訟法
- ポイント: 行政書士試験の主要科目である「憲法」「行政法」は公法に属します。
- 私法(Private Law):国民(個人や法人)同士の関係を規律する法です。個人の自由な意思に基づいた活動(契約など)を尊重します。
- 例: 民法、商法
- ポイント: 行政書士試験の主要科目である「民法」「商法(会社法)」は私法に属します。
(2) 実体法と手続法
- 実体法:権利・義務の内容そのものや、法律関係の実体を定める法です。
- 例: 民法(売買契約の効力や相続人の範囲)、刑法(犯罪の種類と刑罰)
- 手続法:実体法で定められた権利・義務を実現するための手続を定める法です。
- 例: 民事訴訟法(裁判の手順)、刑事訴訟法(捜査や裁判の手順)、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法(これらは行政書士試験の重要科目!)
(3) その他の分類
- 国内法と国際法: ある国の領域内で適用されるか(国内法)、複数の国や国際機関に適用されるか(国際法)による分類。
- 成文法と不文法: 文章として明文化されているか(成文法)、明文化されていないが社会で承認されているか(不文法)による分類。
2.1.3 法の基本原則:法の支配と法治主義
「法の支配」と「法治主義」は、近代国家における法の重要な基本原則です。
- 法の支配(Rule of Law):
- 権力者を含むすべての人が、法に従わなければならないという考え方です。
- 「人による支配」ではなく、「法による支配」を目指し、権力の恣意的な行使を制限し、国民の権利・自由を保障することを目的とします。
- ポイント: 立憲主義(憲法に基づいて政治を行うこと)の根本原理であり、憲法の重要な考え方です。
- 法治主義(Legalism / Rule by Law):
- 国家のすべての活動は、あらかじめ定められた法律に基づいて行われなければならないという考え方です。
- 権力行使の根拠を法律に求める点に重点があります。
- ポイント: 特に行政活動において重要な原則であり、行政法の基礎となります。
【ひっかけポイント】
「法の支配」と「法治主義」は似ていますが、ニュアンスが異なります。
- 法の支配は「どんな法でも良いわけではなく、人権を保障する“良い法”によって権力を縛る」という目的志向の考え方です。
- 法治主義は「必ず法に基づいて行われるべきだが、その法の中身が悪法でも許容する可能性」を含み得る、という点で区別されます。現代においては「法の支配」がより普遍的な原則とされています。
2.2 憲法と法律の関係、条約との関係
法には様々な種類がありますが、それらの法には優劣関係(序列)があります。この序列を理解することは、法律問題を考える上で非常に重要です。
2.2.1 法の序列(階層構造)
日本の法体系は、以下のような階層構造になっています。上位の法は下位の法に優越し、下位の法は上位の法に違反することはできません。
- 憲法(最高法規)
- 条約、法律(国会の制定する法)
- 命令(内閣・各省庁の制定する法規)
- 条例(地方公共団体の議会の制定する法規)
- 規則(地方公共団体の長が制定する法規)
2.2.2 憲法と法律の優劣
- 憲法(Constitution):
- 国の最高法規であり、国の統治の基本原則、国民の基本的人権の保障などを定めた最も重要な法です。
- 国会の制定する「法律」や、その他のあらゆる法は、憲法に違反することはできません。
- もし、法律が憲法に違反している場合(違憲の場合)は、その法律は無効となります。この判断を行うのが裁判所の違憲審査権です(憲法第81条)。
- 法律(Statute):
- 国会が制定する法であり、国民の権利義務を具体的に定めるものです。
- 憲法の下位に位置し、憲法の定めに違反することは許されません。
【ポイント】
「法律」は、国会が国民の代表によって議論し制定する民主的なルールです。しかし、その「法律」でさえ、国民の基本的人権を保障する「憲法」に反することはできない、という点で、憲法が「最高法規」と呼ばれる理由があります。
2.2.3 条約の位置づけ
条約(Treaty)は、国家間の合意であり、国際社会における国家間の権利義務を定めたものです。国際的な合意である条約は、国内法体系においてどこに位置づけられるかが問題となります。
日本の憲法第98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定めています。
この条文の解釈については様々な学説がありますが、行政書士試験対策としては、以下の理解が重要です。
- 条約は、国内法において「法律と同等」か「法律より優位」な地位を持つと考えられています。
- 法律より優位説: 憲法に反しない限り、法律に優先して適用されるとする考え方(通説・判例の傾向)。つまり、条約は法律よりも上位に位置すると解釈されることが多いです。
- 憲法と条約の関係: 憲法が国の最高法規である以上、条約であっても憲法に違反することは許されないという点が確立されています。
【整理】
憲法 > 条約 ≧ 法律 > 命令 > 条例・規則
2.3 法源と判例・慣習法
「法源(ほうげん)」とは、「法がどこから生まれるか、どのような形で存在するのか」という意味です。私たちは、成文化された法律だけでなく、判例や慣習といった様々な形で法に出会います。
2.3.1 成文法と不文法
- 成文法(Codified Law):
- 文書の形で制定され、明文化されている法のことです。
- 日本の中心的な法源であり、明確性と安定性があるという特徴があります。
- 例: 憲法、法律、命令、条例、規則、条約など。
- 不文法(Uncodified Law):
- 文書の形では存在しないが、法としての効力を持つとされている法のことです。
- 社会での慣習や、裁判所の判断の積み重ねによって形成されます。
- 例: 判例法、慣習法、条理など。
2.3.2 判例法(判例の役割)
- 判例(Judicial Precedent):
- 過去の裁判における裁判所の判断(判決・決定など)のことです。
- 日本の裁判制度は、特定の判例に厳格な拘束力を持たせる「判例法主義」を原則としてはいません(個々の判決は、その事案にのみ適用されるのが原則)。
- しかし、最高裁判所の判例は、下級裁判所を事実上強く拘束します。なぜなら、最高裁の判断に反する判決を下せば、上訴されて最終的に最高裁で破棄される可能性が高いからです。
- そのため、実務上、また試験対策上も、重要な最高裁判所の判例は事実上の法源として非常に大きな意味を持ちます。
【ポイント】
行政書士試験では、特に憲法、行政法、民法で「重要判例」からの出題が頻繁にあります。判例の事案、争点、裁判所の判断の結論と理由を正確に理解することが、合格への鍵となります。
2.3.3 慣習法
- 慣習法(Customary Law):
- 長年の間に社会で繰り返し行われ、人々によって「法として守るべき」という確信が持たれるようになった慣習のことです。
- 明文化されていなくても、一定の要件を満たせば法としての効力が認められます。
- 例: 商取引における特定の慣習、地方の入会権(いりあいけん)に関する慣習など。
- 民法第92条: 「法令中の公の秩序に関する規定でない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」と定められています。これにより、特定の条件下で慣習が法としての効力を持つことが示されています。
2.3.4 条理
- 条理(Reason / Natural Justice):
- 社会の道理や衡平の理念、ものの筋道のことです。
- 成文法、慣習法、判例法のいずれによっても解決できない場合に、最後の補充的な法源として、裁判官が判断の根拠とすることがあります。
- 例えば、特定の権利義務関係が法律で明確に定められていない場合に、社会通念や公平性の観点から判断が行われることがあります。
【整理】
日本の法源は、成文法が主であり、その不足を判例法、慣習法、条理などの不文法が補充するという構造になっています。試験対策では、特に「法律」「条約」といった成文法と、「重要判例」という不文法に注目して学習を進めましょう。
2.4 権利・義務・法律関係の基礎
法律を学ぶ上で不可欠な、基本的な用語と概念を理解しましょう。これらは、民法だけでなく、全ての法律科目の基礎となります。
2.4.1 権利と義務
- 権利(Right):
- 特定の者(権利主体)が、他者に対して特定の行為を請求したり、特定の利益を享受したりできる、法によって保障された力のことです。
- 例:
- 所有権: 自分の物を自由に使う、収益を上げる、処分する権利。
- 債権: お金を貸した人が、借りた人に対してお金を返してもらう請求権。
- 表現の自由: 自分の考えを自由に発表する権利(憲法上の権利)。
- 【ポイント】 権利には、他者から侵害されないための「請求権」や、物事を自由に決められる「形成権」など、様々な種類があります。
- 義務(Duty):
- 特定の者(義務主体)が、法によって強制される特定の行為をすること、またはしないことです。
- 例:
- 物を買ったら代金を支払う義務(売主に対する買主の義務)。
- 人を傷つけない義務。
- 交通ルールを守る義務。
- 【ポイント】 権利と義務は表裏一体の関係にあることが多いです。誰かが権利を持つとき、それに対応する義務を持つ者がいることが一般的です。
2.4.2 法律関係
- 法律関係(Legal Relationship):
- 法によって規律された権利と義務の関係のことです。
- 例えば、売買契約が成立すると、売主は代金を受け取る「権利」と物を引き渡す「義務」を負い、買主は物を引き渡してもらう「権利」と代金を支払う「義務」を負います。この売主と買主の間の関係が「法律関係」です。
- 法律関係は、人の行為だけでなく、自然の出来事(例: 相続の発生)によっても生じることがあります。
2.4.3 法律上の「事実」と「行為」
法律の世界では、「事実」と「行為」という言葉も重要な意味を持ちます。
(1) 事実(Fact)
- 法律効果の発生・変更・消滅の原因となる、客観的な出来事のことです。
- 人の意思に基づかない「自然的事実」と、人の行為である「人的事実」に分類されます。
- 自然的事実(例):
- 人の死亡: 相続の開始という法律効果が発生します。
- 地震や津波による損害: 不可抗力による損害賠償責任の免除などの法律効果に影響します。
- 時の経過: 時効の完成、期間の満了など(権利の取得や消滅に影響)。
- 人的事実(例):
- 人の行為: 契約を結ぶ、物を壊すなど。
- 人の心理状態: 悪意、善意など。
- 自然的事実(例):
(2) 行為(Act)
- 人の意思に基づいて行われる、法律効果を発生させるための行動のことです。
- 大きく「適法行為」と「違法行為」に分けられます。
- 適法行為: 法に適合する行為。
- 法律行為:
- 行為者の意思表示に基づいて、その意思表示通りの法律効果を発生させる行為。
- 例: 契約(売買契約、賃貸借契約など)、遺言、代理権の授与。
- 【ポイント】 民法の中心概念の一つであり、行政書士試験でも非常に重要です。意思表示の瑕疵(錯誤、詐欺、強迫)などが問題となります。
- 準法律行為:
- 行為者の意思表示を伴わないが、法律が特定の法律効果を発生させると定めている行為。
- 例:
- 意思の通知: 債務の履行の催告(履行遅滞の責任を発生させる)。
- 感情の表示: 親族による許し(親族間の扶養義務を発生させる)。
- 事実の通知: 債権譲渡の通知。
- 観念の通知: 承認、追認(時効の完成猶予、相続の承認など)。
- 法律行為:
- 違法行為: 法に違反する行為。
- 不法行為:
- 故意または過失によって他人の権利を侵害し、損害を与えた場合に、損害賠償義務を負う行為(民法第709条以下)。
- 例: 交通事故で人を傷つける、他人の物を壊す。
- 債務不履行:
- 契約や法律によって発生した債務を、正当な理由なく履行しない行為。
- 例: 売買契約で代金を支払わない、物を引き渡さない。
- 不法行為:
- 適法行為: 法に適合する行為。
【整理】
法律問題では、まず「どのような事実」があり、その「事実」から「どのような法律効果」が発生するのかを考えます。その際、「人の行為」が関わる場合は、それが「法律行為」なのか「準法律行為」なのか、あるいは「不法行為」なのかなどを判断し、適用される法規を見極めることが重要です。
2.5 裁判制度と訴訟の種類
法律が社会で機能するためには、そのルールが守られない場合に、紛争を解決する仕組みが必要です。その中心的な役割を担うのが裁判制度です。
2.5.1 日本の裁判所の構成
日本には、大きく分けて以下の4種類の裁判所があります。これらの裁判所がそれぞれ役割分担し、日本の司法制度を支えています。
- 最高裁判所:
- 日本の司法の最高機関であり、唯一の裁判所です。
- 終審(最終審)を行う裁判所であり、下級裁判所の判決に対する上告などを審理します。
- 違憲審査権を持ち、法律や命令が憲法に違反していないかを判断する最終的な権限があります。
- 高等裁判所:
- 全国に8ヶ所(本庁)と6ヶ所(支部)あります。
- 地方裁判所や家庭裁判所の判決に対する控訴審(第二審)を主に担当します。
- 地方裁判所:
- 全国に50ヶ所(本庁)と203ヶ所(支部)あります。
- 民事・刑事事件の第一審を主に担当します。事件の規模や内容によって、少額訴訟や簡易裁判所の管轄となる場合もあります。
- 行政事件訴訟の第一審も地方裁判所の管轄です。
- 家庭裁判所:
- 全国に50ヶ所(本庁)と203ヶ所(支部)あります。
- 家族関係に関する事件(離婚、相続、子の養育費など)や、少年事件(非行事件)などを専門に扱います。
- 簡易裁判所:
- 全国に438ヶ所あります。
- 比較的少額の民事事件(訴額140万円以下の請求)や、比較的軽微な刑事事件(罰金以下の刑に当たる事件など)の第一審を扱います。
【ポイント】
日本の裁判制度は三審制(または二審制)を原則としています。第一審で不服があれば控訴(第二審)、さらに不服があれば上告(第三審)と、原則として最大3回まで審理を受けられる仕組みです。
2.5.2 訴訟の種類
裁判所で扱われる訴訟は、大きく3つの種類に分けられます。
(1) 民事訴訟
- 私人(個人や法人)間の財産上の紛争や権利義務に関する争いを解決するための訴訟です。
- 例:
- 売掛金が支払われないので請求したい。
- 隣の土地との境界線を確認したい。
- 交通事故の損害賠償を請求したい。
- 離婚や相続に関する争い(これらは家庭裁判所での手続きが多いですが、最終的に民事訴訟に移行することもあります)。
- 当事者: 原告(訴えを起こす人)と被告(訴えられる人)。
- 目的: 権利関係の確定、損害の賠償など。
(2) 刑事訴訟
- 犯罪が行われた場合に、国家が犯人の責任を追及し、刑罰を科すかどうかを決定するための訴訟です。
- 例: 窃盗、傷害、殺人などの事件。
- 当事者: 検察官(国家を代表して犯人を追及する)と被告人(犯罪を疑われている人)。
- 目的: 犯罪の有無の認定、刑罰の決定。
- 【ポイント】 行政書士試験では、直接の出題は少ないですが、他の法律との関連で概念を理解しておくことが重要です。
(3) 行政訴訟
- 行政機関の行為(行政処分など)に不服がある国民が、その処分が違法であるとして取り消しなどを求める訴訟です。
- 行政書士試験の最重要科目である「行政事件訴訟法」で詳しく学習します。
- 例:
- 営業許可の申請が不当に拒否されたので取り消したい。
- 税金を不当に課されたので無効であることを確認したい。
- 特定の行政行為をすべきなのに行政庁が何もしないので、その違法性を確認したい。
- 当事者: 原告(訴えを起こす国民)と被告(原則として行政処分を行った行政庁が属する国または地方公共団体)。
- 目的: 行政行為の適法性の判断、国民の権利利益の救済。
【整理】
行政書士試験では、特に行政訴訟(行政事件訴訟法)と、民法に関連する民事訴訟の基本的な概念を理解することが重要です。