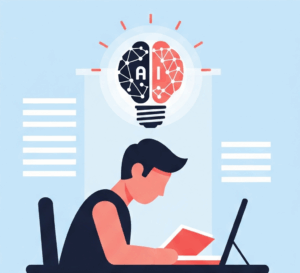
憲法は、私たちの生活の土台となる国の最高法規であり、行政書士試験でも配点の高い重要科目です。特に、基本的人権と統治機構の二本柱をしっかりと理解することが合格への鍵となります。
この章では、日本国の最高法規である「憲法」について深く掘り下げていきます。憲法は、単なる法律のルールブックではありません。国家がどのように組織され、どのように国民を統治し、そして何よりも国民一人ひとりの自由と権利をいかに保障するかという、国のあり方を定めた最も基本的な法です。行政書士試験では、憲法の基礎原理から人権、統治機構まで幅広く問われます。この章を通して、憲法の「なぜ?」を理解し、得点源にしていきましょう。
3.1 憲法の基本原理:国民主権・平和主義・基本的人権の尊重
日本国憲法は、その前文と第一章で、国家の根本的なあり方を示す三大基本原理を掲げています。これらは、憲法の条文を読み解く上での「羅針盤」となる重要な概念です。
3.1.1 国民主権の原理
国民主権とは、国の政治のあり方を最終的に決定する権力(主権)が、国民にあるという原理です。これは、戦前の「天皇主権」から「国民主権」へと大転換した、日本国憲法の最も重要な特色の一つです。
(1) 国民主権の意義
- 主権の所在: 国家の最高意思決定権は国民にあります。国民こそが、国の主人であるという考え方です。
- 代表民主制: 国民が直接政治を行うのではなく、国民が選んだ代表者(国会議員など)を通じて政治を行うという形(間接民主制・代表民主制)が採られています。これは、全国民が常に政治に参加することは現実的ではないためです。
- 憲法制定権: 国民は、憲法を制定し、また改正する権力(憲法制定権)を持ちます。日本国憲法が「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたる自由と平和を確保し…(前文)」と述べているのは、この国民主権の表れです。
(2) 天皇の地位と国民主権
日本国憲法は、国民主権を定めつつも、天皇を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と位置づけています(憲法第1条)。天皇は政治に関する権能を持たず、その地位は国民の総意に基づくとされています。これは、国民主権の原理と両立する象徴天皇制を採用していることを示します。詳細は「3.2 天皇と象徴天皇制」で解説します。
【ポイント】
国民主権は、単なる政治理念ではなく、憲法改正や最高裁判所裁判官の国民審査など、具体的な制度に現れています。
3.1.2 平和主義の原理
平和主義とは、恒久の平和を希求し、戦争を放棄し、戦力を持たず、交戦権を否認するという原理です(憲法第9条)。これは、第二次世界大戦の悲惨な経験を踏まえて採用されました。
(1) 憲法第9条の条文
【日本国憲法第9条】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(2) 第9条の解釈と自衛隊
憲法第9条の解釈は、現在でも大きな議論の的となっています。特に「戦力の不保持」と「交戦権の否認」が、自衛隊の存在や集団的自衛権の行使とどう整合するのかが問題となります。
- 通説的見解: 日本が主権国家である以上、自衛のための必要最小限度の実力を持つことは憲法第9条に反しないとされています。自衛隊は、この「必要最小限度の実力組織」であると解釈されています。
- 集団的自衛権: 日本自身が攻撃されていない場合でも、密接な関係にある他国への武力攻撃を排除するために武力を行使する権利です。この権利の行使が憲法9条と整合するかは、憲法学上も継続的な議論があります。
【ポイント】
行政書士試験では、第9条の条文知識と、自衛隊の合憲性に関する政府見解や主要な学説の概要を理解しておくことが求められます。
3.1.3 基本的人権の尊重の原理
基本的人権の尊重とは、すべての国民が生まれながらにして持つ、人間らしく生きるための不可侵の権利を、国家が最大限に尊重し保障するという原理です。
(1) 人権の普遍性
- 人権は、国家の成立以前から存在する「自然権」であり、国家が与えるものではなく、「国家も侵すことができない」絶対的な権利と考えられています。
- 日本国憲法は、第11条で「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と定め、人権の普遍性と永久性を強調しています。
(2) 人権保障の努力義務
- 憲法第12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」と規定しています。これは、人権が国家によって与えられるものではなく、国民自身が主体的に保持し、発展させていくべきものであるという考え方を示しています。
- また、「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とも規定されており、人権の行使には公共の福祉による制約が伴うことが示唆されています(詳細は「3.7 人権の限界と制約」で解説)。
【ポイント】
基本的人権の尊重は、憲法第13条の「幸福追求権」を包括的な人権として位置づけ、具体的な様々な人権の基盤となっています。行政書士試験では、この原理がどのような具体的な人権(精神的自由権、経済的自由権、社会権など)に展開されるかを問われます。
3.2 天皇と象徴天皇制
日本国憲法は、国民主権を基本原理としながらも、天皇を国の象徴とする象徴天皇制を採用しています。この独特な制度は、行政書士試験でも頻繁に問われる重要ポイントです。
3.2.1 天皇の地位:象徴としての天皇
- 憲法第1条:
【日本国憲法第1条】 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 - 天皇は「主権者」ではなく、「象徴」です。政治的な実権は持ちません。
- その地位は、国民の最終的な意思(国民の総意)に基づいています。これは、国民主権の原理と象徴天皇制が両立していることを示します。
- 「日本国民統合の象徴」とは、天皇が国民全体の精神的な一体感や心のよりどころであることを意味します。
3.2.2 天皇の国事行為と内閣の助言と承認
- 憲法第7条:
【日本国憲法第7条】 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 外国の大使及び公使を接受すること。 九 儀式を行ふこと。 - 天皇は、国政に関する権能(政治的な判断や決定をする権力)を持っていません(憲法第4条1項)。
- 天皇が行うことができるのは、憲法に定められた「国事行為」のみです。
- 国事行為は、「内閣の助言と承認」を必要とします(憲法第3条)。この「助言と承認」がなければ、天皇は国事行為を行うことができません。
- さらに、「内閣が、その責任を負う」とされており(憲法第3条)、天皇が政治的責任を負わない仕組みになっています。
【ひっかけポイント】
- 天皇は「国政に関する権能を有しない」が、「国事行為は行う」という点。
- 国事行為には「内閣の助言と承認」が必要であり、その責任は内閣が負うという点。
- 例: 天皇が法律を「公布」することは国事行為ですが、法律を「制定」する権能はありません(制定するのは国会)。
3.2.3 摂政(せっしょう)
- 天皇が、精神・身体の重患や事故などで国事行為を自ら行えない場合に、天皇の代理として国事行為を行うのが摂政です(皇室典範第16条)。
- 摂政は、天皇の名で国事行為を行います。
3.3 基本的人権の総論
「基本的人権の尊重」は、憲法の最も重要な原理の一つです。ここでは、人権の種類や人権制約の考え方といった、人権に関する基本的な知識を体系的に学びます。
3.3.1 基本的人権の意義と性質
- 意義: 人間が生まれながらにして持っている、人間らしく生きるために必要不可欠な権利で、国家権力によっても侵すことができないものです。
- 性質:
- 固有性: 人間である以上当然に持っている権利。
- 不可侵性: 国家であっても侵すことができない。
- 普遍性: すべての人に等しく保障される。
- 永久性: 現在だけでなく将来にわたって保障される。
3.3.2 人権の種類と分類
日本国憲法が保障する基本的人権は多岐にわたりますが、一般的に以下の種類に分類されます。
- 自由権:
- 国家からの干渉を受けず、自由に活動できる権利。近代憲法の中心をなす人権です。
- さらに精神的自由権(思想・良心、表現、信教など)と経済的自由権(財産権、居住移転、職業選択など)に分けられます。
- 特徴: 国家に「~するな」と不作為(何もしないこと)を求める権利(国家からの自由)。
- 社会権:
- 人間らしい生活を送るために、国家に対して積極的な作為(政策やサービス)を求めることができる権利。20世紀以降に発展した人権です。
- 例: 生存権、教育を受ける権利、労働基本権など。
- 特徴: 国家に「~せよ」と作為(何かをすること)を求める権利(国家による自由)。
- 参政権:
- 国民が政治に参加し、国の意思決定に影響を与えることができる権利。
- 例: 選挙権、被選挙権、国民審査権、憲法改正の国民投票権など。
- 請求権:
- 国家に対して一定の行為を求めることができる権利。
- 例: 裁判を受ける権利、国家賠償請求権、刑事補償請求権など。
- 新しい人権:
- 情報化社会や環境問題など、現代社会の変化に伴って主張されるようになった人権。憲法に明記されていないが、憲法13条の幸福追求権を根拠に認められると考えられています。
- 例: 環境権、プライバシー権、知る権利、日照権など。
3.3.3 公共の福祉による人権の制約
基本的人権は「侵すことのできない永久の権利」ですが、無制限ではありません。他者の人権や社会全体の利益のために、一定の制約を受けることがあります。これを「公共の福祉」による制約と呼びます(憲法12条、13条、22条など)。
(1) 公共の福祉の意義
- 公共の福祉とは、社会全体の利益や共通の幸福を意味します。
- 特定の私人の人権行使が、他の私人の人権や社会全体の利益と衝突する場合に、その人権を調整したり制限したりする根拠となります。
(2) 制約の要件と限界
- 人権の制約は、「必要最小限度」でなければなりません。いたずらに人権を制限することは許されません。
- 制約の目的が「正当」であり、その手段が「合理性」を持っている必要があります。
- 「二重の基準論」: 精神的自由権(思想、表現、信教の自由など)は、人間の精神活動の根幹に関わるため、経済的自由権よりも厳格な基準で審査されるべきという考え方です。これは、精神的自由権が民主政治の基盤となることから、より手厚く保障されるべきであるという趣旨です。
【ポイント】
公共の福祉による制約は、行政書士試験で重要です。人権の制約が合憲かどうかを判断する際に、「必要最小限度」や「二重の基準論」といった概念が使われることを理解しておきましょう。
3.3.4 人権保障の歴史と現代的課題
人権は、歴史的に様々な闘いや努力を通じて獲得されてきました。
- マグナ・カルタ(1215年、イギリス): 国王の権限を制限し、自由と権利を保障する最初の試み。
- 権利の章典(1689年、イギリス): 議会の優位を確立し、国民の権利を保障。
- アメリカ独立宣言(1776年): 人間の不可侵の権利を明記。
- フランス人権宣言(1789年): 自由、平等、抵抗権などを宣言。
- ワイマール憲法(1919年、ドイツ): 世界で初めて社会権を明記した憲法。
- 日本国憲法(1946年公布): 国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を三大原則とし、広範な人権を保障。
現代においても、人権保障には新たな課題が生まれています。例えば、情報化社会におけるプライバシー権や忘れられる権利、環境破壊に対する環境権、LGBTQ+の権利など、社会の変化に対応した人権保障のあり方が常に問われています。これらは「新しい人権」として憲法13条の幸福追求権を根拠に議論されることが多いです。
3.4 精神的自由権:思想・良心・信教の自由
精神的自由権は、個人の内面や精神活動に関する自由を保障する人権で、民主主義の根幹をなす最も重要な人権とされています。試験でも頻出かつ重要判例が多く、詳細な理解が求められます。
3.4.1 思想・良心の自由(憲法第19条)
【日本国憲法第19条】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
- 意義: 人間がどのようなことを考え、どのような価値観を持つか、その内心の自由を保障するものです。
- 特徴: 精神的自由権の中でも最も根源的な自由であり、絶対的に保障されると考えられています。内心の段階にある限り、国家がこれに干渉することは許されません。
- 判例:
- 「内心の自由」は外部に表明されない限り制約されない(例: 政治的信条を内心で持つこと自体は自由)。
- ただし、外部に表現された場合には、他の人権や公共の福祉との関係で制約を受ける可能性があります(例: 表現の自由との関係)。
3.4.2 表現の自由(憲法第21条)
【日本国憲法第21条】
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
- 意義: 自分の思想や意見を外部に発表する自由、また他者の意見を知る自由を保障するものです。民主主義社会を支える基盤となります。
- 保障範囲:
- 表現の内容(何を表現するか)だけでなく、表現の手段(どう表現するか)も含まれます(例: 言論、出版、集会、デモ、放送、インターネットなど)。
- 知る権利: 国民が政府の活動などについて情報を得る権利も、表現の自由の保障に含まれると考えられています。
- 取材の自由: 報道機関が情報を収集する自由も、表現の自由を実質的に保障するために重要です。
- 検閲の禁止: 国家が、表現が発表される前にその内容を審査し、不適当と判断したものを発表させないこと(事前抑制)は、厳格に禁止されています。
(1) 表現の自由の制約と限界
表現の自由は重要ですが、無制限ではなく、他の人権(プライバシー権、名誉権など)や公共の福祉との衝突が生じる場合に制約されることがあります。
- 事前抑制の原則禁止: 検閲は禁止されるだけでなく、表現が発表される前にその内容を禁止・制限すること(事前抑制)は、原則として許されません。例外的に許されるのは、「明白かつ現在の危険」がある場合など、極めて限定的な場合に限られます(例: 博多駅事件判例)。
- 明確性の原則: 表現の自由を制約する法律は、その内容が不明確であってはなりません。
- 表現行為の性質による制約の差異: 表現の手段や内容によっては、制約の程度が異なることがあります。
- 集会・デモ: 事前の届け出制は合憲(許可制は原則違憲)。騒音や交通妨害など、他者の生活に影響を及ぼす場合は一定の制約を受ける。
- わいせつ表現: 公共の性秩序を乱すものは、一定の制約を受ける(刑法上のわいせつ物頒布罪など)。
- 名誉毀損: 他者の名誉を不当に侵害する表現は、損害賠償や刑事罰の対象となる。
(2) 重要判例(表現の自由)
- 泉佐野市民会館事件(泉佐野市における集会不許可事件):
- 争点: 市民会館が特定の政治的意見を持つ団体の集会利用を拒否できるか。
- 判旨: 公の施設は、特定思想の普及目的の利用であっても、公共の施設としての性格に照らし、利用を拒否できるのは、その施設が特定の目的に供され、その目的に反する場合や、利用によって施設が毀損されるような客観的な事情がある場合に限られる。単に、特定の政治的意見を持つことのみを理由に利用を拒否することは許されない。
- 博多駅事件:
- 争点: 鉄道敷地内でのデモ行進を事前に禁じたことが表現の自由の事前抑制にあたるか。
- 判旨: 事前抑制は原則として禁止されるが、「明白かつ現在の危険」がある場合に限り、例外的に許される。本件では、列車の運行に具体的な危険が生じる可能性があったため、禁止は合憲とされた。
- ビラ配布事件(東京都公安条例違反):
- 争点: 公園で許可なくビラを配布したことが都公安条例違反に問われた事件。
- 判旨: 公園でのビラ配布は、思想伝達の重要な手段であり、その自由を保障すべき。条例による許可制は合憲だが、その運用は必要最小限度にとどまるべき。
3.4.3 信教の自由(憲法第20条)
【日本国憲法第20条】
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
- 意義: 宗教を信仰する自由、信仰しない自由、特定の宗教を強制されない自由などを保障するものです。
- 保障範囲:
- 信仰の自由: どのような宗教を信じるか、信じないかの自由。
- 宗教的行為の自由: 礼拝、布教、集会などの宗教活動を行う自由。
- 宗教的結社の自由: 宗教団体を設立し、活動する自由。
- 政教分離の原則:
- 国家と宗教が分離していること。国家が特定の宗教を優遇したり、宗教に干渉したりすることを禁じます(20条1項後段、2項、3項)。
- 目的: 宗教が政治に不当に介入することを防ぎ、また、国家が国民に特定の宗教を強制したり差別したりすることを防ぐためです。
(1) 政教分離の原則と限界
政教分離は厳格に適用されますが、社会生活と宗教が全く無関係ではいられないため、「目的効果基準」という判例法理が用いられます。
- 目的効果基準: 国家の行為が、①宗教的目的を持たず、かつ、②宗教に対する効果が、特定の宗教に援助・助長・促進、または圧迫・干渉となるような「相当なもの」でない限り、合憲と判断する基準。
- 重要判例:
- 津地鎮祭訴訟:
- 争点: 公共工事の地鎮祭に公金を支出したことが政教分離原則に反するか。
- 判旨: 目的効果基準を提唱し、「社会の慣習化した行為であり、宗教的意義は希薄で、宗教との関わり合いが相当とされる限度を超えない」として合憲と判断。
- 愛媛玉串料訴訟(靖国神社玉串料違憲訴訟):
- 争点: 知事が靖国神社に玉串料を公費から支出したことが政教分離原則に反するか。
- 判旨: 目的効果基準に基づき、継続性や金額の規模、宗教的意義などを総合考慮し、違憲と判断。
- 空知太神社訴訟(政教分離原則と公金支出):
- 争点: 神社への土地無償譲渡等が政教分離原則に反するか。
- 判旨: 違憲と判断。目的効果基準を適用し、当該行為が宗教団体を援助・助長する効果を持つと認定。
- 津地鎮祭訴訟:
3.5 経済的自由権:財産権・居住移転の自由
経済的自由権は、国民が自由に経済活動を行い、財産を所有・利用する自由を保障する人権です。精神的自由権に比べ、「公共の福祉」による制約を受けやすいという特徴があります。
3.5.1 財産権(憲法第29条)
【日本国憲法第29条】
1 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
- 意義: 個人が財産を所有し、自由に使用、収益、処分する権利を保障するものです。
- 特徴: 憲法29条2項で「公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」と明記されており、自由権の中でも特に制約を受けやすい性質を持っています。これは、財産が社会と密接に関わるため、社会全体の利益のために調整される必要があるからです。
(1) 財産権の制約と正当な補償
- 「内容の形成」と「個別的制限」:
- 内容の形成: 財産権の内容や行使の態様を、社会全体の利益を考慮して一般的なルールとして法律で定めること(例: 建築基準法、農地法など)。これ自体は、原則として補償を必要としません。
- 個別的制限: 特定の個人の財産権を、特別な必要性に基づいて個別具体的に制限すること(例: 土地収用)。この場合は、「正当な補償」が必要となります(憲法29条3項)。
- 正当な補償の意義:
- 完全補償説(判例・通説): 制限がなければ得られたであろう利益と同等の財産的価値を補償すべきという考え方。単に損失を補填するだけでなく、財産権の移転による損失を完全に補償すべきとされます。
(2) 重要判例(財産権)
- 森林法共有林分割制限事件:
- 争点: 森林法が共有林の分割を制限していることが財産権を侵害しないか。
- 判旨: 森林の公益性や林業政策の重要性から、共有林の分割制限は公共の福祉による財産権の内容形成にあたり、合憲であると判断。補償は不要とした。
- 河川付近地制限令事件:
- 争点: 河川付近での建築を制限する法令が財産権の侵害にあたるか。
- 判旨: 河川の公共性から、公共の福祉による制約であり、合憲と判断。補償は不要とした。
3.5.2 居住・移転の自由(憲法第22条1項)
【日本国憲法第22条1項】
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
- 意義: 日本国内のどこに住むか、どこへ移動するか、またどの職業を選ぶかを自由に決定できる権利です。
- 特徴: 「公共の福祉に反しない限り」という文言が明記されており、最初から公共の福祉による制約が内在していることを示唆しています。
- 海外への移住・外国からの帰国: 憲法第22条2項で保障されています。
【日本国憲法第22条2項】 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。外国への移住の自由は保障されますが、犯罪者などについては海外渡航が制限されることがあります。
3.5.3 職業選択の自由(憲法第22条1項)
- 意義: どのような職業に就くか、またその職業をどのように行うかを自由に選択できる権利です。
- 制約の許容性:
- 判例: 職業選択の自由に対する制約は、その目的や手段の合理性によって合憲性が判断されます。
- 特に、国民の生命や健康、安全に関わる職業(医師、弁護士、薬剤師など)については、免許制度や営業規制といった「消極目的規制(危険防止目的の規制)」が広く許容されます。
- 一方、特定の産業を育成するなど、「積極目的規制(経済政策目的の規制)」については、より厳格な合理性が求められる傾向があります。
【重要判例(職業選択の自由)】
- 薬事法事件(薬局の距離制限に関する判例):
- 争点: 薬局の開設に一定の距離制限を設けることが職業選択の自由を侵害しないか。
- 判旨: 当時、薬局の設置基準は「消極目的規制(国民の健康保護)」の目的であるとされ、その合理性が認められ合憲と判断。「薬事法事件の合憲性判断は、二重の基準論における経済的自由権への比較的緩やかな審査基準を示した」とされる。
- 【ポイント】 この判例は、経済的自由権への規制の合憲性を判断する際の基準として非常に重要です。
3.6 社会権:生存権・教育を受ける権利
社会権は、国民が人間らしい生活を送るために、国家に対して積極的な作為(具体的な施策やサービス)を求めることができる権利です。20世紀以降に登場した新しい人権であり、現代国家の重要な機能の一つを示します。
3.6.1 生存権(憲法第25条)
【日本国憲法第25条】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
- 意義: 国民が、健康で文化的な最低限度の生活を送れるよう、国に保障を求める権利です。
- 特徴:
- プログラム規定説: 憲法25条は、国家の目標や努力義務を定めた「プログラム規定」であり、個々の国民が国に対して直接、具体的な生活保護などを請求する権利(具体的な法的権利)ではないとする考え方(判例・通説)。
- 法的権利説: 憲法25条は、国家に具体的な政策を義務付けるだけでなく、国民が直接、具体的な権利として行使できるとする考え方。
- 【現状】: 判例はプログラム規定説を採用しつつも、国の裁量権の限界を逸脱・濫用した場合には、違法として救済される可能性を示唆しています。
(1) 重要判例(生存権)
- 朝日訴訟(健康で文化的な最低限度の生活):
- 争点: 生活保護基準が憲法25条に違反するほど低すぎるのではないか。
- 判旨: プログラム規定説を採用し、憲法25条は国民が国に直接具体的な生活保護を請求できる権利を定めたものではないと判断。生活保護基準の決定は、厚生大臣の広範な裁量に委ねられるとし、その裁量権を逸脱・濫用しない限り、違憲とはならないとした。
- 堀木訴訟(障害福祉年金と憲法25条):
- 争点: 障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止規定が憲法25条に反しないか。
- 判旨: 憲法25条は直接個人の具体的な請求権を認めたものではないが、法律の合憲性を判断する際の「基準」となるとした。本件では、社会政策上の理由から併給禁止規定は合憲と判断された。
【ポイント】
生存権は、試験では「プログラム規定説」と関連判例が頻出です。直接の法的権利ではないが、立法府の裁量に限界がある、という判例の立場を理解しましょう。
3.6.2 教育を受ける権利(憲法第26条)
【日本国憲法第26条】
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
- 意義: 国民がその能力に応じて、ひとしく教育を受けることができる権利です。
- 特徴:
- 「法律の定めるところにより」: 教育内容や方法については、法律(教育基本法、学校教育法など)によって具体的に定められることを意味します。
- 「能力に応じて」: 個人の能力や特性に応じた教育を受ける機会が保障されることを意味します。
- 保護者の義務: 国民は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負います。
- 義務教育の無償: 義務教育は無償とされますが、これは授業料を徴収しないという意味であり、教科書代や給食費などは含まれないと解釈されています。
3.6.3 労働基本権(憲法第27条、第28条)
- 意義: 労働者が使用者との間で対等な立場に立つために保障される権利です。
- 保障される権利:
- 勤労の権利(27条1項): 働く意思と能力のある者が、国家に対して仕事を与えることを要求できる権利。
- 勤労の義務(27条2項): 「勤労は、国民の権利であり、義務である。」と規定されていますが、これは道徳的義務であり、強制されるものではありません。
- 団結権(28条): 労働者が労働組合を結成する権利。
- 団体交渉権(28条): 労働組合が使用者と賃金や労働条件について交渉する権利。
- 団体行動権(28条): 労働者がストライキなどの争議行為を行う権利。
【ポイント】
公務員の場合、「全体の奉仕者」という性質上、労働基本権が一部制約されることがあります。例えば、公務員にはストライキ権が認められていません。
3.6.4 参政権(憲法第15条、第43条など)
- 意義: 国民が国の政治に参加する権利です。国民主権の原理を具体化する重要な権利です。
- 主な参政権:
- 選挙権: 議員などを選ぶ権利。
- 被選挙権: 議員などに立候補できる権利。
- 国民審査権: 最高裁判所裁判官の国民審査に参加する権利(憲法79条2項)。
- 憲法改正の国民投票権: 憲法改正の承認に関する国民投票に参加する権利(憲法96条)。
- 地方自治における直接請求権: 条例の制定・改廃請求、監査請求など(地方自治法で規定)。
3.7 人権の限界と制約
基本的人権は「侵すことのできない永久の権利」ですが、その行使は無制限ではありません。他の人権や社会全体の利益(公共の福祉)との調整が必要です。また、国民でない者や法人にどこまで人権が保障されるかも重要な論点です。
3.7.1 公共の福祉による制約(再確認)
- 意義: 憲法が人権条項の中で「公共の福祉に反しない限り」と規定しているように、人権の行使は、社会全体の利益や他の個人の人権を侵害しない範囲でなければならないという原則です。
- 二重の基準論:
- 精神的自由権: 思想、表現、信教の自由など。精神的活動の根幹に関わり、民主主義の基礎となるため、厳格な基準(厳格審査基準、明白かつ現在の危険の原則など)で制約の合憲性が判断されます。制約は、必要かつ合理的な範囲で、最小限度にとどめるべきとされます。
- 経済的自由権: 財産権、職業選択の自由など。社会公共の利益との調整が不可欠なため、精神的自由権に比べ、比較的緩やかな基準(合理性基準、明白に不合理でない限り合憲)で制約の合憲性が判断されます。
- 【ポイント】 この二重の基準論は、判例における人権制約の合憲性判断の重要な枠組みであり、試験でも頻出です。
3.7.2 私人間効力(しじんかんこうりょく)
- 意義: 憲法は、本来国家と個人との関係を規律する法(国家権力から個人を守るための法)です。しかし、私人(企業や個人)間の関係で、憲法で保障された人権が侵害されるような場合、憲法の規定をどのように適用できるかが問題となります。これを「私人間効力」といいます。
- 主要な学説と判例の立場:
- 直接適用説: 私人間の関係にも憲法の規定が直接適用されるとする考え方。
- 間接適用説(判例・通説): 私人間の関係には憲法の規定が直接適用されるのではなく、民法などの私法を通じて「間接的」に適用されるとする考え方。
- 判例は、民法の「公序良俗(民法90条)」や「権利の濫用(民法1条3項)」といった一般条項を介して、憲法の趣旨が私人間の関係に及ぶと解釈しています。
- 【ポイント】 特に企業の採用差別(三菱樹脂事件)や、大学の卒業認定(学問の自由との関係)などで問題となります。
- 重要判例(私人間効力):
- 三菱樹脂事件:
- 争点: 企業が思想・信条を理由に採用を拒否したことが憲法14条(平等原則)に違反しないか。
- 判旨: 間接適用説を採用し、企業のような私人は、原則として憲法上の平等原則の直接的な適用を受けないと判断。憲法14条の趣旨は、民法などの私法を通じて間接的に私人間の関係に影響を及ぼす可能性があるが、本件では企業が採用の自由を持つことを優先し、合憲とした。
- 三菱樹脂事件:
3.7.3 外国人・法人の人権
(1) 外国人の人権
- 原則: 日本国憲法が保障する基本的人権は、「国民」という言葉が使われていても、その性質上、外国人も享有できるとされています。
- 例: 思想・良心の自由、表現の自由、信教の自由、身体の自由など。
- 例外(保障されない人権や制約を受ける人権):
- 参政権: 国民主権の原理に基づき、原則として外国人には認められません。ただし、地方公共団体の選挙権については、法律で定めることで付与できるという見解もあります(永住外国人地方参政権訴訟で最高裁は合憲としたが、立法府の判断に委ねた)。
- 入国の自由・在留の自由: 外国人には、憲法上、日本への入国や日本への在留を要求する権利は保障されていません。国家の裁量に委ねられます。
- 再入国の自由: 一度日本に適法に在留している外国人が、一時出国後に日本に再入国する自由は、居住移転の自由(22条)の趣旨から保障されるべきとされています(マクリーン事件判例)。
- 重要判例(外国人の人権):
- マクリーン事件:
- 争点: 在留期間更新許可申請の拒否が、外国人の憲法上の権利を侵害しないか。
- 判旨: 外国人には、憲法上、日本への入国・在留の自由は保障されない。ただし、一度適法に在留した外国人には、憲法22条の趣旨から「在留の継続の期待権」や「再入国の自由」は保障され、その処分は裁量権の逸脱・濫用がない限り合法とされた。
- マクリーン事件:
(2) 法人の人権
- 原則: 法人(会社、NPO法人など)も、その性質が許す限り、基本的人権を享有できるとされています。
- 例: 財産権、営業の自由、表現の自由、裁判を受ける権利など。
- 性質上認められない人権: 身体の自由、生存権、親族に関する権利など、人間の身体や精神に特有の人権は認められません。
- 重要判例(法人の人権):
- 八幡製鉄事件:
- 争点: 会社(法人)が、政治献金をする自由(表現の自由)を持つか。
- 判旨: 法人も自然人と同じく、性質上可能な限り、精神的自由権を含む基本的人権を享有できると判断。政治献金も表現活動の一環として、その自由が認められるとした。
- 八幡製鉄事件:
3.8 統治機構:国会・内閣・裁判所
日本国憲法は、国家権力を「国会(立法)」「内閣(行政)」「裁判所(司法)」の三つに分け、それぞれに役割と権限を与えています。この三権分立の仕組みは、権力の濫用を防ぎ、国民の自由と権利を保障するための重要な原則です。
3.8.1 三権分立の原則
- 意義: 国家権力を複数の機関に分け、それぞれが相互に抑制・均衡し合うことで、特定の機関への権力集中を防ぎ、国民の権利・自由を保障するための仕組みです。
- 抑制と均衡(チェック・アンド・バランス):
- 国会→内閣: 内閣不信任決議権、行政の監視。
- 国会→裁判所: 弾劾裁判所による裁判官の罷免。
- 内閣→国会: 衆議院の解散権。
- 内閣→裁判所: 最高裁判所長官の指名、裁判官の任命。
- 裁判所→国会・内閣: 違憲審査権、行政訴訟による行政行為の審査。
3.8.2 国会(立法権)
- 憲法第41条:
【日本国憲法第41条】 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 - 国権の最高機関: 政治的に最高の地位にあることを示すものであり、他の機関に対する優位性を示すものです。
- 国の唯一の立法機関(立法権の独占): 法律を制定できるのは国会だけであり、他の機関は原則として法律を制定できません。
- 例外: 命令や条例など、法律の下位規範は他の機関も制定します。
- 二院制: 衆議院と参議院の二つの議院から構成されます。
- 衆議院の優越: 予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名、法律案の再議決、内閣不信任決議など、多くの点で衆議院が参議院より強い権限を持っています。
3.8.3 内閣(行政権)
- 憲法第65条:
【日本国憲法第65条】 行政権は、内閣に属する。 - 行政権の主体: 内閣が国の行政事務を最終的に決定し、執行する権限を持ちます。
- 議院内閣制:
- 内閣は国会の信任に基づいて成立し、国会に対して連帯して責任を負う制度です。
- 内閣総理大臣の指名: 国会が国会議員の中から内閣総理大臣を指名します。
- 内閣不信任決議: 衆議院が内閣不信任決議を行った場合、内閣は総辞職するか衆議院を解散しなければなりません。
- 内閣と国会の連携: 内閣が提出した法案は国会で審議され、承認を得る必要があります。
- 内閣の職務: 法律の執行、外交関係の処理、条約の締結、予算の作成、政令の制定など。
3.8.4 裁判所(司法権)
- 憲法第76条:
【日本国憲法第76条】 1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 - 司法権の主体: 裁判所が、法に基づいて具体的な争いを解決する権限(司法権)を持ちます。
- 司法権の独立: 裁判官は、その良心に従い独立して職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束されます。他の機関からの干渉を受けません(憲法76条3項)。
- 違憲審査権: 裁判所は、法律や命令、処分などが憲法に適合するかどうかを審査する権限(違憲審査権)を持ちます(憲法81条)。
- 特別裁判所の禁止: 特定の事件や特定の人物だけを扱うような裁判所(例: 軍法会議)の設置は禁止されています。行政機関が最終的な判断を下すことも禁止されています。
3.9 違憲審査制と憲法改正
国家の最高法規である憲法のルールが守られているかをチェックする仕組みが違憲審査制です。また、時代とともに変化する社会に対応するため、憲法を改めるための憲法改正の仕組みも重要です。
3.9.1 違憲審査制
- 意義: 裁判所が、国会が制定した法律や、内閣が制定した命令、行政機関の処分などが、憲法に適合しているかどうかを審査する制度です。もし憲法に違反していれば、その法律や命令、処分は無効となります。
- 憲法第81条:
【日本国憲法第81条】 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 - 最高裁判所の役割: 最高裁判所が、違憲審査を行う最終的な権限を持ちます。下級裁判所も違憲審査権を持ちますが、最終的な判断は最高裁に委ねられています。
- 付随的違憲審査制: 日本の違憲審査制は、具体的な事件の解決に必要な場合にのみ、その事件に適用される法令の合憲性を審査するという「付随的違憲審査制」を採用しています。
- 【ポイント】 国民が直接「この法律は違憲だから無効にしてください」と裁判所に訴えることはできません。具体的な事件が起こり、その解決のために法律の合憲性が問題となった場合に初めて、裁判所が違憲審査を行うことができます。
- 違憲判断の効力:
- 裁判所が法律を違憲と判断しても、その法律が直ちに廃止されるわけではありません。
- その法律は、当該事件においては適用されず、無効となります。
- しかし、最高裁が違憲と判断した場合、他の同種の事件でも同様の判断が下される可能性が高くなり、事実上、その法律は効力を失ったに等しい状態になります。最終的には、国会がその法律を改正または廃止することになります。
3.9.2 憲法改正
憲法は国の最高法規であり、その改正は一般的な法律の改正よりも厳格な手続きが求められます。
- 憲法第96条:
【日本国憲法第96条】 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、これを公布する。
(1) 憲法改正の手続き(厳格性)
- 国会の発議:
- 衆議院と参議院のそれぞれで、総議員の3分の2以上の賛成が必要です。これは、通常の法律の議決(出席議員の過半数)よりもはるかに厳しい要件です。
- 国民への提案と承認:
- 国会が発議した改正案は、国民に提案され、国民投票によってその承認を得なければなりません。
- 国民投票では、有効投票の過半数の賛成が必要です。
- 天皇の公布:
- 国民の承認を得た後、天皇が国民の名でこれを公布します。この公布は国事行為です。
【ポイント】
- 憲法改正の手続きが厳格であることから、日本国憲法は「硬性憲法」と呼ばれます。
- これは、憲法が国家の基本原則を定めた重要な法であるため、安易な改正を防ぎ、その安定性を保つための仕組みです。
(2) 憲法改正の限界
- 憲法改正は、国民主権や基本的人権の尊重といった憲法の「基本原理」そのものを変更するようなことはできないとする考え方があります(憲法改正の限界説)。
- 例えば、国民主権を否定し、再び天皇主権に戻すような改正は許されない、という議論です。
- ただし、この限界の範囲については、学説上議論が分かれています。