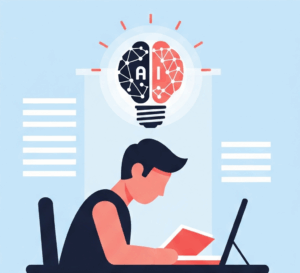
前章の「行政法総論」で、行政活動の全体像や基本的な概念を学びました。本章では、行政法の中でも特に重要な法律の一つである「行政手続法」を詳しく見ていきます。
行政手続法は、行政が許認可や命令、指導といった活動を行う際に守るべき具体的なルールを定めた法律です。行政の独断を排除し、国民の権利利益を守るための、いわば「行政と国民の対話のルールブック」です。ここでの学習が、次の行政不服審査法や行政事件訴訟法の理解を大きく助けます。
5.1 行政手続法の目的と適用範囲
5.1.1 行政手続法の趣旨と原則
行政手続法は、行政の活動を公正に行い、その透明性を高めることで、国民の権利利益を保護することを目的としています(第1条)。
この法律は、以下の3つの基本的な原則に基づいて行政手続を定めています。
- 公正手続の原則:行政は、公平かつ公正に手続を進めなければなりません。
- 手続の透明性の原則:行政は、行政運営における意思決定の過程や内容を明確にし、国民に分かりやすく示さなければなりません。
- 適正手続の原則:行政は、行政手続を適正に行うことで、国民の正当な権利を侵害しないようにしなければなりません。
5.1.2 適用範囲と適用除外
行政手続法は、行政機関が行うすべての行政活動に適用されるわけではありません。法律の趣旨に鑑み、以下のような場合は適用が除外されます(第3条)。
- 国会の両院、議院、議院の委員会、国会の役員が行う処分。
- 裁判所や裁判官が行う処分。
- 刑事事件や少年保護事件に関する処分。
- 出入国管理や外国人の在留資格に関する処分。
- 租税の賦課徴収に関する処分。
【ポイント】
行政書士試験では、「行政手続法が適用されない例外」が頻出です。特に、国会や裁判所の行為、刑事事件や租税の賦課徴収は代表的な適用除外なので、しっかり覚えておきましょう。
5.2 申請に対する処分に関する手続
国民が許認可などを求めて行政に「申請」をした場合、行政はどのようなルールで対応すべきかを定めています。
5.2.1 審査基準と標準処理期間
- 審査基準:申請が許認可されるための具体的な要件や判断基準のことです。
- 行政庁は、審査基準を定め、行政上の便宜を図るためにこれを公表する努力義務を負います(第5条)。
- これにより、申請者は事前に許可の可能性を判断でき、行政の恣意的な判断を防ぎます。
- 標準処理期間:申請が行政庁に到達してから、処分を行うまでに通常要する期間のことです。
- 行政庁は、標準処理期間を定め、公表する努力義務を負います(第6条)。
- これにより、行政の事務処理の遅延を防ぎ、国民はいつまでに処分が下されるかを知ることができます。
【ポイント】
「審査基準」と「標準処理期間」は、いずれも公表は努力義務にとどまり、義務ではありません。しかし、行政書士試験では、この努力義務の性質を問う問題がよく出ます。
5.2.2 申請の処理と理由提示
- 申請の処理:行政庁は、申請が法令に定められた方式に適合しているかを確認します。不備がある場合は、申請者に補正を求めなければなりません(第7条)。
- 理由提示:申請が拒否された場合、行政庁は必ず、その拒否理由を明確に示さなければなりません(第8条)。
- これにより、国民はなぜ申請が認められなかったのかを理解し、不服があれば適切な救済手続(行政不服審査や行政訴訟)を求めることができます。
5.3 不利益処分に関する手続
行政が国民の権利を制限したり、義務を課したりする「不利益処分」を行う際の手続きを定めています。
5.3.1 不利益処分の意義と原則
- 不利益処分とは、行政庁が、特定の者に対し、直接に義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます(第2条4号)。
- 例: 飲食店への営業停止命令、医師免許の取消処分、税金の追加徴収など。
- 不利益処分の原則:不利益処分を行う際には、行政庁は、その処分に慎重な判断をしなければなりません。
5.3.2 聴聞と弁明の機会付与
不利益処分を行う際には、国民に意見を述べる機会を保障しなければなりません。その手続きには、「聴聞」と「弁明の機会付与」の2種類があります。
- 聴聞:
- 要件:許認可等の取消し、停止、はく奪など、比較的重大な不利益処分を行う場合に必要とされます(第13条1項)。
- 手続:聴聞の通知から始まり、主宰者の司会のもとで、利害関係人や行政庁が口頭で意見を述べ、証拠を提出します。
- 目的:公開の場で意見を聴取し、適正な処分を行うための証拠や情報を収集します。
- 弁明の機会付与:
- 要件:聴聞の対象とならない不利益処分の場合に必要とされます。
- 手続:行政庁が、弁明書を提出するか、または口頭で弁明する機会を与えます。
- 目的:不利益処分を受ける者に行政側の主張を伝え、反論の機会を与えます。
【ひっかけポイント】
- 聴聞と弁明の機会付与は、原則として書面で行います。しかし、聴聞は口頭でも意見を述べられる機会を与える点で異なります。
- 聴聞は、「不利益処分がなされる前」に行われる手続です。処分が下された後に争うのは、行政不服審査法や行政事件訴訟法の領域となります。
5.4 行政指導に関する手続
行政法総論でも学んだ「行政指導」は、行政手続法でその手続きが明確化されています。
- 行政指導の原則:行政指導は、あくまでも相手方の任意の協力を前提に行われなければなりません。
- 行政指導を行う者は、その目的を達成するために必要な最小限の範囲で行うべきであり、不当に国民の権利を侵害してはなりません(第32条)。
- 行政指導が相手方の不利益を伴う場合でも、書面交付を求めることができます(第35条)。
- 行政指導の中止等:
- 行政指導が、その根拠となる法律の趣旨に照らして不当である場合には、相手方は、行政庁に対して、その行政指導の中止を求めることができます(第36条の2)。
- これにより、国民は、事実上の強制力を持つ違法な行政指導から救済される道が与えられました。
5.5 届出に関する手続
「届出」とは、行政機関に対し、法令に基づく一定の事項を通知する行為をいいます。
- 届出の義務:
- 法令で義務付けられた届出は、形式上の要件(書式、添付書類など)が満たされている限り、行政庁に到達した時点で、届出としての義務が履行されたことになります(第37条)。
- 届出を受理するか否かは、行政庁の裁量ではなく、法令に適合しているかどうかで判断されます。
- 届出の処理:
- 届出の提出先が複数ある場合、法令で定められている提出先に提出すれば、他の提出先への提出は不要となります(第38条)。
5.6 命令等を定める手続(意見公募手続)
行政が国民の権利義務に影響を与えるルール(命令等)を定める際の手続きです。
- 意見公募手続(パブリックコメント手続):
- 要件:国民の権利義務に直接影響を与える命令等を定める場合には、行政庁は、事前に案を公表し、広く国民から意見を募集しなければなりません(第39条)。
- 目的:行政が定めるルールに、国民の意見を反映させ、行政運営の公正性と透明性を確保することにあります。
- 例外:
- 緊急を要する場合や、軽微な変更の場合など、意見公募手続が不要となる例外も定められています。
【ポイント】
「意見公募手続」は、行政が「新しいルール」を作る段階の手続です。一方、「聴聞」や「弁明の機会付与」は、行政が「個別の国民に対して不利益処分」を行う段階の手続です。この違いを理解することが重要です。