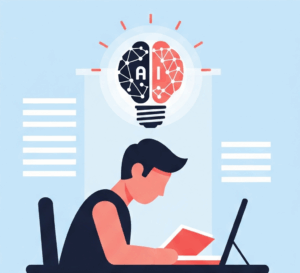
前章で学んだ行政手続法は、行政の活動が公正に行われるための事前のルールでした。この行政救済法は、行政の違法または不当な活動によって国民が不利益を被った場合に、その救済を求めるための法律です。
この章で学ぶ法律は、大きく「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「損失補償」の4つに分かれます。これらは、行政に対する不満を、まず行政内部で解決を図り(行政不服審査法)、それでも解決しない場合は裁判所で解決する(行政事件訴訟法)という、二段階の救済体系をなしています。さらに、金銭的な救済を求めるためのルールも学びます。
6.1 行政不服審査法:不服申立ての基礎
行政不服審査法は、国民が行政庁の処分に不服がある場合に、行政機関に再度、その処分の見直しを求めるための手続を定めた法律です。裁判所に行く前に、まず行政内で解決を図る、という点が特徴です。
6.1.1 不服申立ての種類と対象
不服申立てには、主に以下の2種類があります。
- 審査請求:
- 対象:行政庁の処分や、法令に基づく申請に対する不作為(何も処分しないこと)です。
- 意義:国民の権利利益を直接的に侵害する処分や不作為に対して、行政庁に再検討を求めるものです。
- 原則:すべての審査請求は、法律に特別な定めがない限り、不服申立ての対象となります。
- 再調査の請求:
- 対象:特定の処分について、法律に再調査の請求ができる旨の定めがある場合に限られます。
- 意義:行政庁が、その処分について再度調査を行うことを求めるものです。
【ひっかけポイント】
- 行政不服審査法では、異議申立ては廃止されました。現在は「審査請求」が原則的な不服申立てとなります。
6.1.2 審査請求期間
審査請求期間には厳格な定めがあり、期間を過ぎると請求ができなくなります。
- 原則:処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内です。
- 例外:処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年以内です。
6.2 行政不服審査手続:審理と裁決
審査請求がなされた後、どのような流れで審査が進むのかを解説します。
6.2.1 審理員制度
- 意義:公正な審査を確保するため、審査請求の審理は、処分に関与していない「審理員」が行います。
- 手続:審理員は、審査請求人(国民)や、原処分庁(処分を行った行政庁)から意見を聴取し、証拠書類を調べます。
- 役割:審理員は、審理の結果を「審理員意見書」にまとめ、裁決庁(最終的な判断を下す行政庁)に提出します。
6.2.2 裁決の種類と効力
裁決とは、審理結果に基づいて、審査請求に対する最終的な判断を下す行政行為です。
- 裁決の種類:
- 却下裁決:審査請求が要件(期間など)を満たしていない場合に、内容の是非を判断せず請求を却下する裁決です。
- 棄却裁決:審査請求に理由がない場合に、請求を退ける裁決です。
- 認容裁決:審査請求に理由がある場合に、請求を認める裁決です。
- 裁決の効力:
- 認容裁決がなされると、その処分は取消しや変更がなされます。
- 裁決には公定力や既判力といった特別な効力はありませんが、拘束力があります。
- 拘束力:裁決を下した行政庁や、その下級行政庁は、その裁決に従わなければなりません。
6.3 行政事件訴訟法:行政訴訟の種類と特徴
行政事件訴訟法は、行政の違法な活動によって国民が被った不利益を、裁判所の判断によって救済するための手続を定めた法律です。
6.3.1 抗告訴訟
抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に対する不服を訴える訴訟です。
- 取消訴訟:違法な行政処分の取消しを求める訴訟です。最も代表的な行政訴訟です。
- 無効等確認訴訟:行政処分の無効の確認を求める訴訟です。公定力がなく、最初から無効である場合に提起されます。
- 不作為の違法確認訴訟:行政庁が法令に基づく申請に対し、相当な期間内に何もしない(不作為)場合に、その違法性を確認する訴訟です。
- 義務付け訴訟:行政庁が特定の処分を行うべき義務があるにもかかわらず行わない場合に、その義務を果たすよう命じる訴訟です。
- 差止訴訟:行政庁が特定の処分を行うおそれがある場合に、その処分を差し止めるよう命じる訴訟です。
6.4 取消訴訟の要件と手続
行政訴訟の中心である取消訴訟を提起するためには、以下の重要要件を満たす必要があります。
- 原告適格:訴えを提起する者が、法律上の利益を持つ者であること。単なる事実上の利益では認められません。
- 被告適格:訴えの相手方となる行政庁が国または公共団体であること。
- 訴えの利益:訴訟を提起することによって、法的な利益が回復される可能性があること。
- 出訴期間:処分があったことを知った日から6ヶ月以内に提起しなければなりません。ただし、処分があった日から1年以内でも提起可能です。
【ポイント】
行政不服審査の「審査請求期間」と行政事件訴訟の「出訴期間」は、知った日から3ヶ月 vs 6ヶ月、という違いがあります。この期間の違いは頻出なので注意しましょう。
6.5 行政訴訟の判決と効力
裁判所が下す判決の種類とその効力を学びます。
6.5.1 判決の種類
- 認容判決:原告の訴えを正当と認め、処分を取り消す判決です。
- 棄却判決:原告の訴えを理由がないと認め、訴えを退ける判決です。
- 事情判決:処分が違法であるにもかかわらず、その処分を取り消すことによって公共の福祉に著しい影響がある場合に、裁判所が例外的に請求を棄却する判決です。
6.5.2 判決の効力
判決が確定すると、以下のような効力が発生します。
- 既判力:裁判の判決が確定すると、当事者はその内容に二度と争うことができなくなります。
- 形成力:判決によって、処分の法的効力が失われる効力です。
- 拘束力:判決の内容は、関係行政庁を拘束し、同様の違法な処分を繰り返すことを防ぐ効力です。
6.6 仮の救済制度:執行停止・仮の義務付け・仮の差し止め
裁判の判決には時間がかかります。その間に国民が回復不能な損害を被ることを防ぐため、暫定的な措置が認められています。
- 執行停止:処分の執行や手続の続行を一時的に停止する制度です。
- 例: 営業停止命令の取消訴訟中、その営業停止命令の効力を一時的に停止してもらうこと。
- 仮の義務付け:義務付け訴訟の判決を待たずに、行政庁に一時的な義務を課すことです。
- 仮の差し止め:差止訴訟の判決を待たずに、行政庁に一時的な差し止めを命じることです。
6.7 国家賠償法:行政による損害賠償
国家賠償法は、行政の違法な活動によって国民に生じた損害を金銭で補償する法律です。
- 国家賠償法1条(公権力の行使):
- 要件:公権力の行使にあたる公務員が、故意または過失によって違法に国民に損害を与えた場合。
- 効果:国または公共団体が、その損害を賠償する責任を負います。
- 国家賠償法2条(営造物責任):
- 要件:道路、河川、学校などの営造物が、設置または管理の瑕疵(欠陥)によって、国民に損害を与えた場合。
- 効果:国または公共団体が、その損害を賠償する責任を負います。
6.8 損失補償:適法な公権力行使による損失
損失補償は、国家賠償とは異なり、行政の適法な公権力の行使によって、特定の者が特別の犠牲を強いられた場合に、その損失を補うための金銭補償です。
- 意義:「公共の福祉のために特別の犠牲を強いられた者は、公平の観点から補償を受けるべきである」という考え方(平等原則)に基づきます。
- 要件:
- 適法な公権力の行使であること。
- 特定の者に対し、特別の犠牲を課すものであること。
- 例:
- 土地収用(公共事業のために土地が収用される場合)
- 文化財保護法に基づく建物の現状変更の制限など
- 国家賠償との違い:国家賠償が「違法な」行為を対象とするのに対し、損失補償は「適法な」行為を対象とします。この違いは試験で頻出なので、しっかりと区別して覚えましょう。