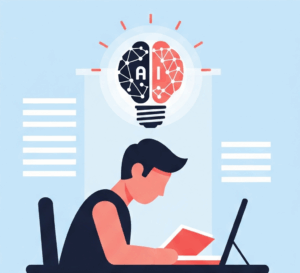
これまでの章では、国全体の行政の仕組みや、国民と行政との関係を律する法律について学んできました。本章では、より身近な「地方自治」に焦点を当て、地方自治法が定める地域の行政とその運営、そして住民の関わり方について詳しく解説します。
地方自治は、私たちの日常生活に密接に関わる行政活動であり、地方自治法は、その具体的なルールを定めた基本法です。地域の課題を地域住民が自らの手で解決していくための仕組みを理解することは、行政書士としても非常に重要です。
7.1 地方自治の基本原理と種類
7.1.1 地方自治の意義
地方自治とは、地域住民の意思に基づき、その地域の行政が自らの責任で行われることを指します。国の行政とは異なり、地域の実情に応じた柔軟な行政運営が可能となり、住民の多様なニーズに対応できる点が特徴です。
7.1.2 住民自治と団体自治
地方自治の原則は、大きく分けて二つの側面から捉えられます。
- 住民自治:
- 意義:地域住民が自らの意思に基づき、直接または間接的に地方公共団体の政治に参加することを指します。
- 具体例:選挙による議員や首長の選出、後述する直接請求制度など。住民の意見が行政運営に反映される仕組みです。
- 団体自治:
- 意義:国から独立した法人格を持つ地方公共団体が、その責任において自律的に行政を行うことを指します。
- 具体例:地方公共団体が条例を制定する権限、国の関与に対する自律性など。国と地方の関係において、地方公共団体の独立性が保障される側面です。
【ポイント】
「住民自治」と「団体自治」は、地方自治法の根幹をなす概念です。この二つが車の両輪となって、地方自治が成り立っています。
7.1.3 普通地方公共団体と特別地方公共団体
地方公共団体は、その性質によって二つに分類されます。
- 普通地方公共団体:
- 意義:都道府県と市町村のことです。
- 特徴:包括的な行政事務を処理し、広範な権限を持ちます。
- 特別地方公共団体:
- 意義:特定の目的のために設置される地方公共団体です。
- 具体例:
- 特別区(東京都の23区):市町村に準ずる機能を持つ。
- 地方公共団体の組合:複数の地方公共団体が共同で事務を処理するために設置(例:消防組合、ごみ処理組合など)。
- 財産区:特定の地域住民の共同の財産を管理するために設置。
7.2 住民の権利と義務:直接請求制度
地方自治においては、住民が行政に直接的に関与できる直接請求制度が設けられています。これは、住民自治の具体的な表れであり、住民の意思を行政に反映させるための重要な手段です。
7.2.1 条例の制定・改廃請求
- 請求権者:その地方公共団体の選挙権を有する者。
- 請求要件:有権者総数の50分の1以上の署名を集めることで請求できます。
- 対象:地方公共団体の条例の制定または改廃を請求できます。
- 手続:請求を受けた長は、請求を議会に提出し、その結果を住民に告示します。
7.2.2 監査請求
- 請求権者:その地方公共団体の選挙権を有する者。
- 請求要件:有権者総数の50分の1以上の署名を集めることで請求できます(住民監査請求)。
- 対象:地方公共団体の財務に関する違法・不当な行為について、監査委員に監査を請求できます。
- 目的:地方公共団体の財政の適正な運営を監視し、住民の税金が適正に使われているかをチェックします。
- 結果:監査の結果、違法・不当な事実が認められた場合、監査委員は勧告を行い、長はその措置を講じなければなりません。
【ポイント】
「50分の1」という数字は、条例の制定・改廃請求と監査請求で共通して重要です。
7.2.3 解散請求(議会の解散請求)
- 請求権者:その地方公共団体の選挙権を有する者。
- 請求要件:有権者総数の3分の1以上の署名を集めることで請求できます。
- 対象:地方公共団体の議会の解散を請求できます。
- 手続:請求を受けた選挙管理委員会は、住民投票に付し、過半数の同意があれば解散が決定します。
7.2.4 解職請求(リコール)
- 請求権者:その地方公共団体の選挙権を有する者。
- 請求要件:有権者総数の3分の1以上の署名を集めることで請求できます。
- 対象:長、副知事・副市町村長、議会の議員、監査委員、選挙管理委員など、主要な役職者の解職を請求できます。
- 手続:請求を受けた選挙管理委員会は、住民投票に付し、過半数の同意があれば解職が決定します。
【ポイント】
議会の解散請求と主要役職者の解職請求(リコール)は、いずれも「3分の1」の署名が必要です。
7.3 地方公共団体の組織:議会と執行機関
地方公共団体の組織は、国と同様に「議会」と「執行機関」に分かれ、それぞれが役割を分担しています。
7.3.1 地方議会の権能
地方議会は、地方公共団体の意思決定機関であり、住民を代表して地域の重要事項を審議・決定します。
- 主な権能:
- 議決権:条例の制定・改廃、予算の議決、重要な契約の締結など。
- 選挙権:議長、副議長の選挙。
- 検査・監査権:地方公共団体の事務の執行状況を検査したり、監査委員に監査を求めたりする権限。
- 意見表明権:国や他の地方公共団体に対して意見を表明する権限。
7.3.2 長の権限
長(都道府県知事、市町村長など)は、地方公共団体の執行機関の長であり、議会の決定に基づいて事務を執行します。
- 主な権限:
- 地方公共団体の代表者として、その事務を総括・管理。
- 予算案や条例案の提出権。
- 議会の議決に対する拒否権(再議請求権):議会の議決が違法または不当と判断した場合、議会に再審議を求めることができます。
- 職員の任免権。
7.3.3 専門委員会の役割
地方公共団体には、特定の専門的な事務を行うために、専門委員会が設置されることがあります。
- 具体例:教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員など。
- 特徴:これらの委員会は、それぞれの専門分野において、独立した権限を行使します。特に、教育委員会や監査委員は、長の指揮監督を受けない独立性が保障されています。
7.4 事務の種類:自治事務と法定受託事務
地方公共団体が処理する事務は、大きく二つの種類に分けられます。この区分は、事務に対する国の関与の程度に影響します。
7.4.1 自治事務
- 意義:地方公共団体が、その固有の事務として、自己の判断と責任で行う事務です。
- 具体例:住民票の発行、戸籍事務、消防事務、都市計画、道路・公園の整備、ごみ処理など。
- 特徴:地方公共団体が条例や規則を制定して自主的に処理できます。国からの関与は、適法性の審査に限定され、その裁量に立ち入ることはできません。
7.4.2 法定受託事務
- 意義:国または都道府県が、法律またはこれに基づく政令により、地方公共団体に処理させる事務です。
- 具体例:旅券(パスポート)の発給、国政選挙の執行、戸籍の登記事務、統計調査など。
- 特徴:地方公共団体が国の機関として処理します。国からの関与は、適法性だけでなく、合目的性(能率性や合理性)についても審査され、国からの指示や助言を受けることがあります。
【ポイント】
「自治事務」と「法定受託事務」の区別は、国がどこまで地方に口出しできるかという点で重要です。国家賠償法や行政訴訟においても、この区分が関わってくることがあります。
7.5 財政と監査制度
地方公共団体が住民サービスを提供するためには、その財源が必要です。また、その財源が適切に使われているかをチェックする仕組みも重要です。
7.5.1 地方公共団体の財政
- 財源:地方税(住民税、固定資産税など)が主な財源ですが、国の支出金(国庫支出金)や地方債(借金)なども利用されます。
- 予算:長が作成し、議会の議決を経て確定します。予算の執行状況は議会や監査委員によってチェックされます。
7.5.2 監査委員と監査請求制度
- 監査委員:地方公共団体の事務や財産の執行が適正に行われているかを監査する機関です。長から独立した立場で職務を行います。
- 選任:議会の同意を得て、長が選任します。
- 種類:包括外部監査(外部の専門家による監査)や、住民監査請求(住民による請求に基づく監査)などがあります。
- 住民監査請求:
- 意義:前述の「住民の直接請求制度」の一つであり、地方公共団体の財務に関する違法・不当な行為について、住民が監査委員に監査を請求できる制度です。
- 手続:住民が、選挙権を有する者総数の50分の1以上の署名を集めて、監査委員に請求します。
- 結果:監査の結果、住民の請求に理由があると認められた場合、監査委員は、長や関係職員に対して、必要な措置(損害賠償請求など)を講ずるよう勧告します。
7.6 国と地方公共団体の関係
国と地方公共団体は、それぞれ独立した行政主体でありながら、密接な関係にあります。
7.6.1 国と地方の役割分担
- 国は、国の存立に関わる事務や、全国的に統一された基準が必要な事務(外交、防衛、通貨、司法など)を主に担当します。
- 地方公共団体は、地域の特性に応じた住民サービスや、地域の実情に合わせた施策(福祉、教育、防災、環境など)を主に担当します。
7.6.2 国の関与(助言、勧告、是正勧告など)
国は地方公共団体に対し、一定の範囲で関与することができます。これは、地方自治を尊重しつつも、国全体の整合性を保つために必要とされます。
- 助言・勧告:
- 国は、地方公共団体に対し、その事務の処理について必要な助言や勧告を行うことができます。これは強制力を持たない、最も緩やかな関与です。
- 是正勧告・指示:
- 地方公共団体の事務処理が法令に違反している場合や、著しく不適当と認められる場合、国は地方公共団体に対し、是正を勧告したり、場合によっては指示をしたりすることができます。特に法定受託事務については、より強い指示が可能です。
- 代執行:
- 地方公共団体が法令で定められた義務を怠り、かつ、その不作為が公益に著しい損害を与える場合には、国が代わりにその事務を執行する代執行が認められることがあります。ただし、これは極めて例外的かつ厳格な要件のもとで行われます。
【ポイント】
国の関与は、地方自治の独立性を尊重しつつ行われるべきであり、その範囲や方法は地方自治法で厳格に定められています。特に「法定受託事務」に対する国の関与は、「自治事務」に対する関与よりも強いものとなります。