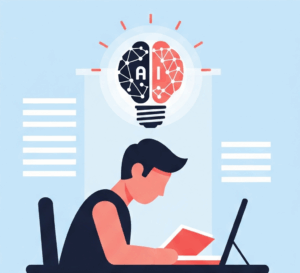
行政書士試験において、民法は最も配点の高い科目の一つであり、その知識は他の法律科目を理解する上でも不可欠です。民法は、私たちの日々の生活や経済活動における「私人間の基本的なルール」を定めています。人、モノ、お金、家族といったあらゆる私的な関係を規律する、まさに法律の基礎となる科目です。
この章では、民法全体を「民法総則」「物権」「債権」「親族・相続」の4つの分野に分けて、それぞれの重要な概念とルールを解説していきます。複雑な条文が多いですが、具体例を交えながら、一つずつ丁寧に理解していきましょう。
8.1 民法総則:権利能力・行為能力・意思表示
民法総則は、民法全体の共通ルールを定めた部分です。人(自然人・法人)がどのように法律関係に参加し、意思表示を行うか、その基本的な枠組みを理解します。
8.1.1 人:権利能力と行為能力
- 権利能力:
- 意義:権利の主体となり、義務を負うことができる法律上の資格を指します。
- 自然人:出生から死亡まで権利能力を有します。胎児は、相続や不法行為による損害賠償など、特定の範囲で権利能力が認められることがあります。
- 法人:法律の規定に基づいて設立され、その目的の範囲内で権利能力を持ちます。
- 行為能力:
- 意義:単独で有効な法律行為を行うことができる能力を指します。
- 原則:満18歳以上の者は、単独で有効な法律行為ができます。
- 制限行為能力者:行為能力が制限されている者。保護者の同意や監督がなければ有効な法律行為ができない場合があります。
8.1.2 制限行為能力者
制限行為能力者が単独で行った法律行為は、原則として取り消すことができます。これは、不慣れな者や判断能力が不十分な者を保護するための制度です。
- 未成年者:
- 原則として、法定代理人(親権者など)の同意を得なければ、有効な法律行為はできません。同意なしに行った行為は取り消すことができます。
- ただし、単に権利を得るだけ、または義務を免れるだけの行為、許された営業に関する行為などは単独で有効です。
- 成年被後見人:
- 精神上の障害により、事理を弁識する能力を常に欠く状態にある者。家庭裁判所が後見開始の審判をします。
- 原則として、単独で行った法律行為はすべて取り消すことができます(日用品の購入などごく一部の例外を除く)。
- 被保佐人:
- 精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な者。家庭裁判所が保佐開始の審判をします。
- 重要な法律行為(例:不動産の売買、借金など)については、保佐人の同意が必要です。同意なしに行った行為は取り消すことができます。
- 被補助人:
- 精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な者。家庭裁判所が補助開始の審判をします。
- 特定の法律行為についてのみ、補助人の同意が必要です。同意なしに行った行為も、その同意を要する行為でなければ原則有効です。
【ポイント】
制限行為能力者の制度は、弱者保護が目的です。誰が、どのような場合に、どの範囲で法律行為を取り消せるのか、また、善意の第三者との関係でどうなるのかが頻出論点です。
8.1.3 意思表示の瑕疵(錯誤、詐欺、強迫)
法律行為は、当事者の意思表示に基づいて効力が生じます。しかし、その意思表示に問題(瑕疵)があった場合、法律行為の効力に影響が出ます。
- 心裡留保(しんりりゅうほ):
- 意義:表意者が真意ではないことを知ってした意思表示(例:冗談)。
- 効力:原則として有効。ただし、相手方が真意でないことを知っていたり(悪意)、知ることができた場合(有過失)は無効。
- 虚偽表示:
- 意義:相手方と通じてした虚偽の意思表示(例:財産隠しのために仮装売買)。
- 効力:常に無効。ただし、善意の第三者には対抗できません。
- 錯誤:
- 意義:表意者が、自分の意思表示と真意が食い違っていることに気づかないまま意思表示をしてしまうこと。
- 効力:取り消すことができます。ただし、錯誤が表意者の重大な過失による場合や、動機の錯誤が相手方に表示されていない場合は、取消しが制限されます。
- 詐欺:
- 意義:騙されて意思表示をしてしまうこと。
- 効力:取り消すことができます。
- 第三者による詐欺の場合、相手方がその詐欺を知っていたり(悪意)、知ることができた場合(有過失)に限り取消しが可能です。
- 強迫:
- 意義:脅されて意思表示をしてしまうこと。
- 効力:取り消すことができます。
- 詐欺と異なり、第三者による強迫の場合でも、相手方の善意・悪意に関わらず取消しが可能です。
【ポイント】
錯誤、詐欺、強迫のいずれも、取り消された場合、その効果は遡及的に失われます(はじめからなかったことになる)。また、善意の第三者を保護する規定があるかどうかが重要です。
8.2 代理と無権代理
代理とは、本人に代わって、代理人が法律行為を行い、その効果が直接本人に帰属する制度です。
8.2.1 代理の意義、種類、要件、効果
- 意義:本人が直接法律行為を行うことができない場合や、効率的に法律行為を行いたい場合に利用されます。
- 種類:
- 任意代理:本人の意思(委任契約など)に基づいて代理権が発生するもの。
- 法定代理:法律の規定に基づいて代理権が発生するもの(例:親権者、成年後見人)。
- 代理の要件:
- 代理権の存在:代理人が本人から代理権を与えられているか、または法律によって代理権が付与されていること。
- 顕名(けんめい):代理人が本人(代理される者)のためにすることを示して意思表示を行うこと(例:「Aの代理人Bとして契約します」)。
- 有効な代理行為:代理人自身が行為能力を有すること。
- 代理の効果:上記の要件を満たした場合、代理人の行為によって生じた法律効果は、直接本人に帰属します。
8.2.2 無権代理の処理
無権代理とは、代理権がないにもかかわらず、代理人と称して法律行為を行うことを指します。原則として本人に効果は帰属しませんが、例外的な処理が可能です。
- 原則:無権代理人の行為は、本人には効果が帰属しません。
- 本人の追認:
- 本人は、無権代理行為を後から「追認」することができます。追認すれば、その行為は遡及的に有効となり、はじめから代理権があったものとして扱われます。
- 追認をしない場合は、本人に効果は帰属しません。
- 相手方の催告権・取消権:
- 無権代理の相手方は、本人に対して追認するかどうかを催告することができます。本人から返答がない場合、追認を拒絶したものとみなされます。
- 相手方は、本人による追認があるまでは、その契約を取り消すことができます。
- 無権代理人の責任:
- 本人が追認せず、かつ相手方が契約を取り消さなかった場合、無権代理人は相手方に対して損害賠償責任を負うか、または契約の履行責任を負います。
【ポイント】
無権代理は、試験で頻繁に出題されます。本人の追認の有無、相手方の選択権、無権代理人の責任が複雑に絡み合うため、それぞれの要件と効果をしっかり整理しましょう。
8.3 期間と時効
8.3.1 期間の計算方法
法律における期間の計算は、民法総則に定められたルールに従います。
- 初日不算入の原則:期間の初日は、原則として期間に算入しません(午前0時から始まる場合は例外)。
- 期間満了:期間が週、月、年で定められた場合、最終日の終了(午後12時)をもって期間が満了します。
- 期間の末日が休日の場合:期間の末日が日曜日や祝日など法律上の休日に当たる場合、期間は翌日まで延長されます。
8.3.2 取得時効と消滅時効
時効とは、ある事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態を尊重して、権利の取得や消滅という法律上の効果を発生させる制度です。
- 取得時効:
- 意義:他人の物を占有し続けることによって、その物の所有権を取得する制度。
- 要件:
- 所有の意思:自己のために占有すること。
- 平穏・公然の占有:争いや隠蔽なく占有すること。
- 一定期間の継続:
- 善意・無過失の場合:10年間
- 悪意または有過失の場合:20年間
- 効果:時効期間が満了すると、占有者はその権利を取得します。
- 消滅時効:
- 意義:権利者が権利を行使しない状態が一定期間継続した場合に、その権利が消滅する制度。
- 要件と期間:
- 債権:
- 権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年間
- 権利を行使できる時(客観的起算点)から10年間
- いずれか早い方で消滅時効が完成します。
- 不法行為による損害賠償請求権:
- 損害及び加害者を知った時から3年間
- 不法行為の時から20年間(除斥期間)
- 債権:
- 効果:時効期間が満了すると、権利は消滅します。
8.3.3 時効の援用と完成猶予・更新(旧中断・停止)
- 時効の援用:
- 時効期間が満了しただけでは、自動的に権利が取得・消滅するわけではありません。時効による利益を受ける者が、「時効の利益を受けます」という意思表示(援用)をすることで、初めて効力が生じます。
- 時効の完成猶予(旧中断):
- 特定の事由(例:裁判上の請求、強制執行、承認など)があった場合、その期間中は時効の進行が一時的に停止し、その事由が終了した後に再び進行を開始します。
- 時効の更新(旧停止):
- 特定の事由(例:判決の確定、強制執行の終了、承認など)があった場合、それまでの時効期間はリセットされ、時効が新たに進行を開始します。
【ポイント】
2020年4月1日施行の改正民法により、時効の「中断」は「完成猶予」と「更新」に、「停止」は「完成猶予」に名称が変更され、その内容もより明確化されました。試験では改正後の内容が問われるので注意が必要です。
8.4 物権総論:物権の種類と効力
物権とは、物を直接的に支配し、排他的な効力を持つ権利のことです。
8.4.1 物権の意義、種類
- 意義:物に対する権利であり、誰に対しても主張できる「対世的効力」を持つのが特徴です。
- 種類:民法で定められた物権は、以下の8種類です(物権法定主義)。
- 占有権:物を事実上支配している状態から発生する権利(本権の有無は問わない)。
- 所有権:物を自由に使用、収益、処分できる最も完全な物権。
- 地上権:他人の土地の上に、工作物や竹木を所有するため、その土地を使用する権利。
- 永小作権:他人の土地で耕作または牧畜をする権利。
- 地役権:自分の土地の便益のために、他人の土地を利用する権利(例:通行地役権)。
- 留置権:他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その債権の弁済を受けるまで物を留置できる権利。
- 先取特権:法律の規定によって特定の債権者が、債務者の特定の財産から他の債権者よりも優先的に弁済を受けられる権利。
- 質権:債権の担保として、債務者または第三者から物を受け取り、その物から他の債権者よりも優先的に弁済を受けられる権利。
- 抵当権:債権の担保として、債務者または第三者が提供した不動産を、占有を移さずに担保とし、債務不履行時にその不動産から他の債権者よりも優先的に弁済を受けられる権利。
【ポイント】
物権の種類は「用益物権(使用・収益を目的とする:地上権、永小作権、地役権)」と「担保物権(債権の担保を目的とする:留置権、先取特権、質権、抵当権)」に分類して理解すると覚えやすいでしょう。
8.4.2 物権的請求権
物権の内容が侵害されたり、侵害されるおそれがある場合に、物権者がその侵害を排除するために認められる請求権です。
- 物権的返還請求権:物を不法に占有されている場合に、その物の返還を求める権利。
- 物権的妨害排除請求権:物に対する妨害が存在する場合に、その妨害の排除を求める権利。
- 物権的妨害予防請求権:物に対する妨害が生じるおそれがある場合に、その予防を求める権利。
8.5 不動産物権変動と対抗要件
不動産の物権(特に所有権)が、売買や相続などによって移転したり変更されたりする際のルールです。
- 物権変動:売買契約などにより、不動産の所有権が移転するなどの変動が生じること。
- 不動産登記制度:
- 不動産の所在地、地番、面積、所有者などを公の帳簿(登記簿)に記録し、公開する制度です。
- これにより、不動産の現状や権利関係を明確にし、取引の安全を確保します。
- 対抗要件主義:
- 民法は、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができないと定めています(民法177条)。
- つまり、不動産を売買して所有権を得たとしても、その事実を登記しておかないと、その不動産が二重に売買された場合などに、登記を備えた他の買主には自分の所有権を主張できない、ということです。
- 登記の重要性:不動産の権利変動においては、登記をすることで初めて、自分がその不動産の正当な権利者であることを第三者に対して主張できるようになります。
【ポイント】
「対抗要件」は、物権変動の重要論点です。登記をすべき「第三者」の範囲や、登記なくして対抗できる場合(例:不法行為者)などが試験でよく問われます。
8.6 債権総論:債権の発生と消滅
債権とは、特定の人(債権者)が特定の人(債務者)に対して、特定の行為(給付)を請求できる権利です。
8.6.1 債権の意義、種類、発生原因
- 意義:債権は、物権と異なり、特定の人に対する請求権であり、直接物を支配する権利ではありません。
- 発生原因:債権は主に以下の原因によって発生します。
- 契約:売買、賃貸借、消費貸借など、当事者の合意によるもの。
- 事務管理:法律上の義務なく他人の事務を処理すること。
- 不当利得:法律上の原因なく他人の財産や労務によって利益を得ること。
- 不法行為:故意または過失により他人に損害を与えること。
8.6.2 債務不履行
債務不履行とは、債務者が債務の内容に従った履行をしないことを指します。債務不履行が発生した場合、債権者は様々な救済を求めることができます。
- 種類:
- 履行遅滞:履行期が過ぎても、履行がされないこと。
- 履行不能:債務の履行が物理的・社会的に不可能になること。
- 不完全履行:履行はされたが、不完全な形であること。
- 効果:
- 損害賠償請求:債権者は、債務不履行によって生じた損害の賠償を請求できます。
- 強制履行:裁判所を通じて、債務者に強制的に履行させることを請求できます。
- 契約解除:債務不履行が重大な場合、契約を解除して、契約がはじめからなかったことにできます。
8.6.3 債権者代位権、詐害行為取消権
債務者が財産を隠匿したり、財産を減らしたりする行為をした場合に、債権者がその債権を保全するための制度です。
- 債権者代位権:
- 意義:債務者が第三者に対して権利を持っているにもかかわらず、その権利を行使しない場合に、債権者が債務者に代わってその権利を行使できる制度。
- 要件:債務者が無資力であること(財産がないこと)、債務者が自ら権利を行使しないことなど。
- 詐害行為取消権:
- 意義:債務者が、債権者を害することを知りながら、自身の財産を不当に減少させる行為(詐害行為)を行った場合に、債権者がその行為を取り消し、財産を元に戻すことを請求できる制度。
- 要件:債務者の行為が債権者を害することを知っていたこと、受益者(詐害行為により利益を得た者)もその事実を知っていたことなど。
8.7 多数当事者の債権・債務
債権者または債務者が複数いる場合に適用されるルールです。
8.7.1 連帯債務、保証債務
- 連帯債務:
- 意義:複数の債務者が、それぞれが債務全額を履行する義務を負い、そのうちの一人が履行すれば他の債務者の義務も消滅する債務。
- 特徴:債権者は、どの連帯債務者に対しても全額の履行を請求できます。連帯債務者の一人が弁済した場合、他の連帯債務者に対して求償権を行使できます。
- 保証債務:
- 意義:主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人がその債務を履行する義務を負う債務。
- 特徴:保証人には、まず主たる債務者に請求するよう求める「催告の抗弁権」や、主たる債務者の財産から強制執行するよう求める「検索の抗弁権」が認められます。
- 連帯保証:保証人が上記の抗弁権を持たず、主たる債務者と同等の責任を負う保証です。金融機関の融資などで多く見られます。
8.7.2 不可分債務、債権譲渡
- 不可分債務:
- 意義:債務の目的が、性質上分割できないものである場合の債務(例:特定の絵画の引き渡し)。
- 特徴:連帯債務に準じて扱われますが、目的が不可分である点が異なります。
- 債権譲渡:
- 意義:債権者が、自分が持っている債権を、第三者(譲受人)に譲り渡すこと。
- 対抗要件:債権が譲渡されたことを債務者や第三者に対抗するためには、債務者への通知または債務者の承諾が必要であり、確定日付のある証書によることが求められます。
8.8 契約総論:契約の成立と効力
契約は、私法上の権利義務を発生させる最も一般的な原因です。
8.8.1 契約の意義、種類、成立要件
- 意義:複数の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為です。
- 種類:民法には様々な種類の契約(典型契約)が定められています(例:売買、賃貸借、請負、委任など)。また、民法に定められていない契約(非典型契約)も自由に結ぶことができます(契約自由の原則)。
- 成立要件:
- 申込みと承諾:当事者間の具体的な申込みと、それに対する承諾の意思表示が合致すること。
- 意思の合致:内容について両当事者の意思が一致していること。
- その他:法律によっては、書面によること(例:保証契約)、または特定の形式(要式行為)を要する場合があります。
8.8.2 契約の効力発生時期、解除権
- 効力発生時期:契約は、原則として申込みと承諾の意思が合致した時点で成立し、効力が発生します(諾成契約の原則)。
- 解除権:
- 意義:一旦有効に成立した契約の効力を、当事者の一方の意思表示によって遡及的に消滅させる権利。
- 種類:
- 法定解除権:債務不履行(履行遅滞、履行不能など)があった場合に、法律の規定に基づいて発生する解除権。原則として、履行の催告が必要です。
- 約定解除権:契約当事者の合意によって、特定の事由が発生した場合に契約を解除できると定めるもの(例:手付解除)。
- 効果:解除により、契約は遡及的に消滅し、当事者は原状回復義務を負います。
8.9 典型契約:売買・賃貸借・請負・委任
民法で定められている代表的な契約について、その特徴と当事者の権利義務を解説します。
8.9.1 売買
- 意義:当事者の一方がある財産権を相手方に移転し、相手方がこれに対して代金を支払うことを約する契約(民法555条)。
- 特徴:諾成契約、有償契約、双務契約。
- 当事者の権利義務:
- 売主:財産権移転義務、契約不適合責任(引き渡した物が種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合の責任。旧瑕疵担保責任)。
- 買主:代金支払義務。
- 手付:売買契約の際に買主が売主に交付する金銭。手付には、契約成立の証拠としての証約手付、解除権を留保する解約手付、債務不履行の際の違約罰としての違約手付などがあります。解約手付の場合、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を償還して、契約を解除できます。
【ポイント】
2020年4月1日施行の改正民法により、旧「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に名称が変更され、その内容も拡充されました。試験では改正後の内容が問われます。
8.9.2 賃貸借
- 意義:当事者の一方がある物を相手方に使用及び収益させることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約する契約(民法601条)。
- 特徴:諾成契約、有償契約、双務契約。
- 当事者の権利義務:
- 賃貸人(貸主):賃借人に対し、目的物を使用・収益させる義務、修繕義務。
- 賃借人(借主):賃料支払義務、契約期間終了後の原状回復義務。
- 敷金、礼金、原状回復義務などの論点も重要です。
8.9.3 請負
- 意義:当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約(民法632条)。
- 特徴:諾成契約、有償契約、双務契約。
- 当事者の権利義務:
- 請負人:仕事完成義務。完成した仕事に不適合がある場合は契約不適合責任を負います。
- 注文者:報酬支払義務。
8.9.4 委任
- 意義:当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約(民法643条)。
- 特徴:諾成契約、無償が原則(特約があれば有償)。
- 当事者の権利義務:
- 受任者(委託された側):善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって委任事務を処理する義務、報酬を受け取る権利(有償の場合)。
- 委任者(委託する側):費用償還義務、報酬支払義務(有償の場合)。
- 準委任:法律行為以外の事務処理を委託する契約(例:医療行為の委託)。委任の規定が準用されます。
8.10 不法行為
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、それによって生じた損害を賠償する義務を負う制度です(民法709条)。
8.10.1 不法行為の成立要件
不法行為が成立し、損害賠償請求ができるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 故意または過失:加害者に故意(意図して損害を与えた)または過失(不注意で損害を与えた)があること。
- 権利侵害または法律上保護される利益の侵害:被害者の生命、身体、財産などの権利や利益が侵害されたこと。
- 損害の発生:侵害によって実際に損害が発生したこと。
- 因果関係:加害者の行為と損害の発生との間に、相当な因果関係があること。
- 責任能力:加害者が、自己の行為の結果を弁識する能力(責任能力)を有すること。
8.10.2 損害賠償請求、特殊な不法行為
- 損害賠償請求:不法行為が成立した場合、被害者は加害者に対して、その損害の賠償を請求できます。原則として金銭による賠償です。
- 特殊な不法行為:民法には、通常の不法行為の要件を修正したり、加害者以外の者が責任を負うとされる特殊な不法行為が定められています。
- 使用者責任(民法715条):被用者(従業員など)が事業の執行に関して第三者に損害を与えた場合、使用者(会社など)も損害賠償責任を負う。
- 工作物責任(民法717条):土地の工作物(建物、道路など)の設置または保存に瑕疵があり、それによって他人に損害を与えた場合、占有者または所有者が損害賠償責任を負う。
- 共同不法行為(民法719条):複数の者が共同して不法行為を行い、損害を与えた場合、連帯して損害賠償責任を負う。
- 責任無能力者の監督義務者責任(民法714条):未成年者や精神上の障害により責任能力のない者が他人に損害を与えた場合、その監督義務者(親権者など)が損害賠償責任を負う。
8.11 事務管理・不当利得
これらの制度は、契約関係がないにもかかわらず、公平の観点から金銭のやり取りや義務の発生を認めるものです。
8.11.1 事務管理
- 意義:法律上の義務なく、他人のために事務の処理を開始すること。(民法697条)
- 成立要件:
- 他人の事務であること。
- 法律上の義務がないこと。
- 他人のためにする意思(事務管理意思)があること。
- 本人の意思または利益に適合すること(原則)。
- 効果:
- 事務管理者:本人に対し、善管注意義務をもって事務を処理し、報告する義務を負います。
- 本人:事務管理者に対し、費用償還義務や債務代弁義務を負います。
8.11.2 不当利得
- 意義:法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を得た者が、その利益を喪失した者に対し、その利益を返還する義務を負うこと。(民法703条)
- 成立要件:
- 他人の財産によって利益を得たこと。
- その利益によって他人が損失を被ったこと。
- 利益と損失の間に因果関係があること。
- 法律上の原因がないこと。
- 効果:受益者は、その利益を不当利得として返還しなければなりません。
- 善意の受益者:利益の存する限度で返還義務を負います。
- 悪意の受益者:受けた利益に利息を付けて返還し、損害があれば賠償する義務を負います。
8.12 親族法:家族関係のルール
親族法は、婚姻、親子関係、扶養、後見制度など、家族関係に関するルールを定めています。
8.12.1 婚姻
- 成立要件:
- 婚姻適齢(男女ともに18歳以上)。
- 双方に婚姻する意思があること。
- 届出(婚姻届)をすること(届出婚主義)。
- 近親婚の禁止などの要件を満たすこと。
- 婚姻の効力:
- 夫婦同氏の原則(改正民法により選択的夫婦別氏の導入が検討されています)。
- 夫婦間の扶養義務、同居・協力・扶助義務。
- 婚姻費用分担義務。
8.12.2 親子関係と扶養
- 親子関係:
- 嫡出子:婚姻中に生まれた子。夫の子と推定されます。
- 非嫡出子:婚姻関係にない男女間に生まれた子。原則として母子関係は出生により発生し、父子関係は認知によって発生します。
- 養子:血縁関係がなくても、養子縁組によって法律上の親子関係を創設できます。
- 扶養:
- 親族間には、生活を困難とする者を助ける扶養義務が発生します。
- 特に、夫婦間、親子の間には、強い扶養義務(生活保持義務)があります。
8.12.3 後見制度
判断能力が不十分な人を保護するための制度です。
- 成年後見制度:精神上の障害により判断能力が不十分な成年者を保護する制度。法定後見(後見、保佐、補助)と任意後見があります。
- 未成年後見制度:未成年者に親権を行う者がいない場合や、親権者が親権を停止された場合に、未成年者を保護する制度。
8.12.4 離婚後共同親権(2025年施行の改正民法に対応)
【重要:2025年施行の改正民法】
2024年4月19日、離婚後の子どもの親権に関する民法などの改正案が国会で可決・成立し、2025年中に施行される予定です。
- 現行制度(施行前):
- 離婚後は、夫婦のどちらか一方が子の単独親権を持つこととされています。共同親権は認められていませんでした。
- 改正後の制度(2025年施行予定):
- 離婚後も、父母が共同して親権を行使する「共同親権」を選択できるようになります。
- ただし、父母が共同親権に合意できない場合は、家庭裁判所が父母のどちらか一方を親権者と定めます。
- 子の利益を最優先に考慮し、父母の対立が激しい場合などは単独親権と判断される可能性もあります。
- 親権の内容には、子の監護及び教育の権利義務に加え、子の財産管理権も含まれます。共同親権の場合、これらの権限を共同で行使することになります。
- 子の養育費や面会交流についても、子の利益を最優先とし、書面での取り決めが努力義務とされます。
【ポイント】
「離婚後共同親権」は、施行が近いため、行政書士試験での出題が予想される最重要改正点の一つです。改正の背景、現行制度との比較、そして「子の利益を最優先」という原則を理解しておく必要があります。
8.13 相続法:財産の承継ルール
相続法は、人の死亡によって、その財産(権利・義務)がどのように承継されるかを定めたルールです。
8.13.1 相続の開始と相続人
- 相続の開始:人の死亡によって相続が開始します。
- 相続人:財産を承継する人です。民法で定められた法定相続人が優先されます。
- 配偶者:常に相続人となります。
- 子:第一順位の相続人。子がいない場合は、直系尊属(父母など)へ。直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹へ。
- 直系尊属:第二順位の相続人(子がいる場合は相続人になりません)。
- 兄弟姉妹:第三順位の相続人(子、直系尊属がいる場合は相続人になりません)。
- 代襲相続:相続人となるべき者が、相続開始前に死亡していた場合などに、その子(孫)が代わりに相続人となる制度。
8.13.2 法定相続分と遺言
- 法定相続分:民法が定めている、各相続人が相続する財産の割合です。
- 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2(子が複数いる場合は均等割り)。
- 配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3。
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。
- 遺言:
- 意義:被相続人が、生前に自分の意思で財産の処分方法を定める行為です。
- 種類:自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、厳格な方式が定められています。
- 効力:遺言は、法定相続分に優先して効力を持ちます。
8.13.3 遺留分、限定承認、相続放棄
- 遺留分:
- 意義:兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限相続できる財産の割合です。遺言によっても奪われることのない権利です。
- 遺留分侵害額請求:遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した者に対し、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できます。
- 限定承認:
- 意義:被相続人の債務(借金など)が、相続財産の範囲内である場合に、その相続財産の限度で債務を承継する方法です。
- 手続:相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
- 相続放棄:
- 意義:被相続人の全ての権利義務(プラスの財産もマイナスの財産も)を一切承継しないこと。
- 手続:相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
【ポイント】
相続法では、法定相続人の範囲と順位、法定相続分、遺言の種類と効力、そして遺留分、限定承認、相続放棄といった重要な概念が頻出です。特に「3ヶ月以内」という期間制限は試験でよく問われます。