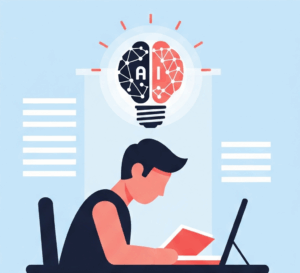
行政書士試験の「一般知識等」科目は、法律科目とは異なり、幅広い分野から出題されるのが特徴です。配点は高めであり、特に足切り点(基準点)が設けられているため、この科目を疎かにすることはできません。
この章では、政治、経済、社会といった時事問題から、現代社会に不可欠な情報通信・個人情報保護、そして行政書士としての業務を規律する法令、さらには合否を分ける文章理解まで、重要ポイントを解説していきます。
10.1 政治・経済・社会の基礎知識
この分野は、私たちの日常生活やビジネスを取り巻く環境を理解するために不可欠な知識です。ニュースや新聞に日頃から目を通し、幅広い視野を持つことが重要になります。
10.1.1 日本の政治体制
- 日本国憲法と三権分立:
- 国会(立法):法律を制定する国の最高機関。衆議院と参議院の二院制。
- 内閣(行政):法律を執行する機関。内閣総理大臣を首長とし、国会議員の中から選ばれる大臣で構成。
- 裁判所(司法):法律に基づき紛争を解決する機関。最高裁判所を頂点とする。
- 【ポイント】 三権分立の原則と、それぞれの機関が持つ抑制と均衡の関係を理解しましょう。
- 選挙制度:衆議院議員選挙の小選挙区比例代表並立制や、参議院議員選挙の比例代表制など、選挙制度の仕組みと特徴。
- 地方自治:第7章で学んだ地方自治法の内容に加え、地方分権の推進や、地方創生といった国の政策動向も重要です。
10.1.2 経済の仕組みと財政
- 市場経済の基本:需要と供給の法則、価格の決定メカニズム。
- マクロ経済指標:GDP(国内総生産)、物価指数(消費者物価指数など)、失業率、為替レートなど、経済状況を示す基本的な指標の意義。
- 財政:国の予算の種類(一般会計、特別会計)、税の種類(所得税、消費税、法人税など)、財政投融資の仕組み。
- 金融:日本銀行の役割(金融政策、物価安定目標、量的緩和など)、金利の変動が経済に与える影響。
10.1.3 社会保障制度
- 社会保障の4本柱:
- 社会保険:医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険。それぞれの制度の目的、加入者、給付内容。
- 社会福祉:高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉など、社会的に支援が必要な人々を対象とするサービス。
- 公衆衛生:感染症対策、食の安全、環境衛生など、国民全体の健康を守るための活動。
- 公的扶助:生活保護制度など、経済的に困窮する国民に対する最低限度の生活保障。
- 【ポイント】 少子高齢化が進む現代社会において、年金制度の持続可能性や医療費の増大など、社会保障制度が抱える課題にも関心を持つことが重要です。
10.1.4 国際情勢と国際関係
- 国際機関:国連(UN)、WTO(世界貿易機関)、IMF(国際通貨基金)など、主要な国際機関の役割と機能。
- 国際経済:自由貿易と保護貿易、経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)の意義。
- 日本の外交:主要国との関係、安全保障政策、国際貢献など。
- 時事問題:過去1年程度の国内外の重要なニュースや社会問題について、背景や影響を含めて理解を深めましょう。
10.2 情報通信・個人情報保護
情報化社会の進展に伴い、この分野の知識は行政書士にとっても不可欠です。特に個人情報保護は、行政書士が業務として扱う機会も多いため、重点的な学習が必要です。
10.2.1 情報セキュリティとネットワーク
- 情報セキュリティの3要素:機密性(情報漏洩防止)、完全性(情報の改ざん防止)、可用性(必要な時に情報が利用できること)。
- サイバー攻撃の手法:フィッシング詐欺、マルウェア(ウイルス、ランサムウェアなど)、DDoS攻撃など。
- 情報セキュリティ対策:パスワード管理、多要素認証、暗号化、バックアップ、ファイアウォール、アンチウイルスソフトなど。
- ネットワークの基礎:インターネットの仕組み、IPアドレス、ドメイン名、Wi-Fiなど。
10.2.2 データ活用の基礎と情報流通プラットフォーム対処法
- ビッグデータ:大量のデータを分析し、ビジネスや社会課題解決に活用する概念。
- AI(人工知能):機械学習、ディープラーニングなどの技術と、その社会への影響。
- IoT(モノのインターネット):様々な「モノ」がインターネットに接続され、相互に情報をやり取りする技術。
- 【重要:2025年4月1日施行】情報流通プラットフォーム対処法
- 正式名称は「情報流通プラットフォーム対処法(情報流通プラットフォーム対処の適正化等に関する法律)」。
- 施行日:2025年4月1日。
- 目的:インターネット上の情報流通プラットフォーム(SNS、動画共有サイト、ECサイトなど)において、違法・有害情報が流通することによる被害を防ぎ、利用者保護を強化すること。
- 主な内容:
- プラットフォーム事業者の義務:違法・有害情報の通報窓口設置、対応体制の整備、迅速な情報削除措置、透明性の確保(情報削除基準の開示など)。
- 対応情報:サイバー暴力、名誉毀損、詐欺、わいせつ情報など、特に問題となる情報の類型が定められます。
- 利用者の権利:違法・有害情報によって被害を受けた利用者が、プラットフォーム事業者に対し、適切な対応を求める権利が強化されます。
- 国の関与:総務省などがプラットフォーム事業者への指導・勧告を行う権限を持つようになります。
- 【ポイント】 デジタル社会の進展に伴い、ネット上の情報トラブルが増加している中で、利用者保護とプラットフォーム事業者の責任を明確化する画期的な法律です。行政書士は、ネットトラブルに関する相談を受けることも増えるため、その概要を理解しておくことが重要です。
10.2.3 個人情報保護法とマイナンバー法
- 個人情報保護法:
- 意義:個人情報(氏名、生年月日、住所など、特定の個人を識別できる情報)の取扱いに関するルールを定めた法律です。
- 基本原則:利用目的の特定、適正な取得、安全管理措置、第三者提供の制限、開示・訂正・利用停止等の請求権など。
- 個人情報保護委員会:個人情報保護に関する行政機関であり、企業などへの指導や監督を行います。
- 【ポイント】 行政書士は業務上、顧客の個人情報を扱うため、この法律の理解は必須です。特に「個人情報取扱事業者」としての義務をしっかり把握しましょう。
- マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律):
- 意義:マイナンバー(個人番号)の利用範囲と取扱いに関するルールを定めた法律です。
- 利用目的の限定:マイナンバーの利用は、社会保障、税、災害対策の3分野に厳しく限定されています。
- 安全管理措置:マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の厳格な安全管理措置が義務付けられています。
- 【ポイント】 行政書士が税や社会保険関連の手続を代行する場合など、マイナンバーを扱う機会があります。その利用目的の限定や安全管理義務を理解しましょう。
10.3 行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令
行政書士は、行政書士法という法律に基づいて業務を行う国家資格者です。行政書士としての心構えや、守るべきルールを理解することは、資格取得後の実務において最も重要です。
10.3.1 行政書士法
- 行政書士の職務:
- 官公署に提出する書類の作成:許認可申請、届出、契約書など。
- 権利義務に関する書類の作成:契約書、遺産分割協議書、内容証明郵便など。
- 事実証明に関する書類の作成:実地調査に基づく図面、会計帳簿など。
- 上記に関する相談業務:書類作成に付随する相談に応じること。
- 特定行政書士:行政書士が作成した書類について、行政庁に対する不服申立ての手続を代理できる。
- 行政書士の登録:行政書士となるには、行政書士試験に合格し、日本行政書士会連合会の名簿に登録する必要があります。
- 行政書士法人:複数の行政書士が共同で業務を行う法人形態。
10.3.2 行政書士倫理と職務上の義務
行政書士は、国民の権利利益を守る専門家として、高い倫理観と様々な義務が課せられます。
- 職務上の義務:
- 誠実義務:常に品位を保持し、公正・誠実に職務を行う義務。
- 守秘義務:正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務。
- 公正証書作成等に関する義務:公正証書を作成する際の手続の遵守。
- 帳簿記載義務:業務に関する帳簿を作成し、保存する義務。
- 非弁行為の禁止:弁護士法に抵触するような、訴訟関連の業務を行ってはならない義務。
- 非税理士行為の禁止:税理士法に抵触するような、税務に関する業務を行ってはならない義務。
- 行政書士の倫理綱領:行政書士の行動規範を示したもので、職務遂行上の指針となります。
10.3.3 報酬と登録
- 報酬:行政書士は、依頼者から報酬を受けることができます。報酬額は、日本行政書士会連合会が定める基準(報酬額基準)を参考に、個々の行政書士が自由に設定できます。
- 登録:行政書士になるための登録手続、登録取消し、業務停止などの処分。
10.4 文章理解:正確な読解力と論理的思考力
文章理解は、出題数が少ないながらも、合否を大きく左右する重要な科目です。正確な読解力と論理的思考力を問われるため、日頃から文章に触れ、演習を重ねることが不可欠です。
10.4.1 文章の要旨把握
- 文章全体のテーマや筆者の主張を正確に読み取る能力が問われます。
- 解法:
- 主題文(トピックセンテンス)を見つける。
- キーワードや繰り返し使われる表現に注目する。
- 具体例や補足説明と、筆者の主張を区別する。
- 段落ごとの内容を要約し、全体を統合する。
10.4.2 多肢選択問題の解法
- 与えられた文章に対する適切な選択肢を選ぶ問題。
- 解法:
- まず設問の要求内容を正確に把握する。
- 各選択肢を吟味し、本文との一致度を比較する。
- 本文に書かれていないこと、本文と矛盾すること、極端な表現(「~だけ」「~全て」など)を含む選択肢は注意する。
- 消去法も有効な手段です。
10.4.3 論理的接続詞の理解
- 文章の論理的なつながりを理解するために、接続詞の役割を把握することが重要です。
- 主な接続詞の種類と役割:
- 順接:「したがって」「そのため」「ゆえに」など(原因・理由→結果)。
- 逆接:「しかし」「だが」「ところが」など(期待と異なる結果)。
- 対比・並列:「一方」「また」「あるいは」など(異なる事柄の提示)。
- 添加・補足:「さらに」「しかも」「その上」など(情報を付け加える)。
- 例示:「たとえば」「具体的には」など。
- 結論・要約:「つまり」「要するに」「以上から」など。
- 【ポイント】 接続詞を意識することで、文章の構造や筆者の主張がより明確に理解できます。
10.4.4 文章整序問題の対策
- バラバラにされた文章の断片を、論理的な順序に並べ替える問題。
- 解法:
- まず、各断片の内容を理解する。
- 冒頭文や結論となる文を探す。
- 指示語(「これ」「それ」「その」など)や接続詞に注目し、前後関係を推測する。
- 時間的な流れや因果関係を意識する。
- 具体例は抽象的な説明の後に来る、といった法則を意識する。
- 実際に並べ替えた後に、全体を読んでみて自然かどうかを確認する。
一般知識等は、出題範囲が広い反面、基本的な知識を問われることが多い科目です。日頃からニュースに目を向け、社会の動きに関心を持つことが、効率的な学習につながります。諦めずにしっかりと対策を立てて、足切りをクリアしましょう!