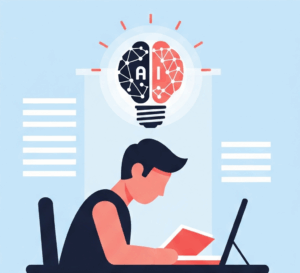
これまでの章で、行政と個人の関係や、個人間の私的なルールである民法について学んできました。本章からは、ビジネス活動を規律する「商法」と、その中心となる「会社法」について学びます。
商法・会社法は、企業活動の基本的なルールを定める法律であり、行政書士が扱う許認可業務や契約業務において、企業との関わりは避けられません。会社の設立から運営、そして解散に至るまでの基本的な知識を身につけることで、実務においても大いに役立つでしょう。
9.1 商法の基本原則と商行為
9.1.1 商法の意義と基本原則
- 商法とは、商取引や商事組織(会社など)に関する私法の特別法です。民法が定める一般的なルールに対し、商法はビジネスにおける特殊性を考慮した規定を設けています。
- 基本原則:
- 営利性:商法は、利益追求を目的とする営利活動を規律します。
- 団体性:会社のような団体組織の活動を重視します。
- 迅速性:商取引の円滑かつ迅速な処理を促進します。
- 定型性:商取引に共通する定型的なルールを設けることで、取引の安全を図ります。
9.1.2 商法の種類
商法は、以下の大まかな区分に分けることができます。
- 商法総則:商人、商号、商業帳簿など、商法の共通ルール。
- 商行為法:売買、代理商、問屋など、商行為に関するルール。
- 会社法:会社の設立、組織、運営、解散などに関するルール。商法典から独立した法律として位置づけられています。
- 手形法・小切手法:手形や小切手に関するルール。
- 保険法:保険契約に関するルール。
9.1.3 商行為の種類
商人が行う行為を商行為といい、民法の特別法として商法の規定が適用されます。商行為は、その性質によって以下の種類に分類されます。
- 絶対的商行為:
- 意義:行為の性質上、常に商行為となるもの。行為者が商人であるか否かにかかわらず、商法の適用を受けます。
- 具体例:営利を目的とした投機売買(転売目的での物品購入)、手形その他の有価証券に関する行為、取引所での取引など。
- 営業的商行為:
- 意義:営利を目的として反復継続的に行われる行為で、特定の業種を営む場合などに商行為となるもの。行為者が商人であるかどうかが重要です。
- 具体例:物品の賃貸、運送、請負、銀行取引、保険など、法律に列挙された事業を営むこと。
- 付属的商行為:
- 意義:商人が営業のために行う行為。直接的には商行為でなくても、営業活動に付随して行われるものです。
- 具体例:会社が事務用品を購入する行為、営業用車両を賃借する行為など。
【ポイント】
商行為の区分は、それぞれの行為に商法のルールが適用されるか否かを判断する基準となります。特に絶対的商行為は、行為者の属性に関わらず商行為となる点が重要です。
9.2 会社法の基本と会社の種類
会社法は、会社という組織の設立、運営、管理、解散など、会社に関する包括的なルールを定めた法律です。現代社会において、ビジネス活動の中心をなすのが会社であり、その仕組みを理解することは必須です。
9.2.1 会社の意義と会社の種類
- 会社とは、商行為を営むことなどを目的とし、営利を追求する法人を指します。
- 会社の種類:
- 株式会社:
- 特徴:株式を発行して出資を募り、株主は出資額を限度として責任を負う(間接有限責任)。株主と経営者が分離している点が特徴です。現代の企業形態の主流です。
- 持分会社:
- 特徴:出資者が直接会社を経営し、出資者(社員)と会社が一体となっている形態です。原則として社員は無限責任を負います(合同会社は有限責任)。
- 種類:
- 合名会社:社員全員が無限責任社員。
- 合資会社:無限責任社員と有限責任社員で構成。
- 合同会社:社員全員が有限責任社員。近年設立が増加しています。
- 株式会社:
【ポイント】
株式会社と持分会社(特に合同会社)の違いは、社員の責任(有限責任か無限責任か)と経営の形態(所有と経営の分離か否か)です。
9.2.2 会社設立の手続
会社を設立するには、法律に定められた厳格な手続を踏む必要があります。ここでは、最も一般的な株式会社の設立手続の概要を解説します。
- 定款の作成:
- 会社の「憲法」にあたるもので、会社の商号(名称)、目的、本店所在地、発行可能株式総数など、会社の基本的なルールを定めます。
- 公証人の認証を受ける必要があります。
- 出資の履行:
- 定款で定めた株式の発行価額を払い込み、または現物出資を行います。
- 発起設立(発起人だけが出資)と募集設立(広く出資を募る)があります。
- 機関の選任:
- 会社の設立時役員(取締役、監査役など)を選任します。
- 設立登記:
- 本店所在地を管轄する法務局に、設立登記を申請します。
- 会社は、登記によって初めて法人として成立します(設立準則主義)。
9.3 株式会社の機関:株主総会・取締役・監査役
株式会社には、会社の意思決定や業務執行、監査を行うための様々な機関が置かれています。
9.3.1 株主総会
- 意義:株式会社の最高意思決定機関であり、全ての株主で構成されます。
- 主な権限:
- 会社の基本事項の決定:定款変更、役員の選任・解任、剰余金の配当、会社の解散など。
- 取締役会設置会社では、業務執行に関する事項は取締役会に委ねられ、株主総会の権限は法律または定款に定められた事項に限られます。
- 招集手続:
- 原則として取締役(取締役会設置会社では取締役会)が招集します。
- 株主総会の招集通知は、会日の2週間前(公開会社以外は1週間前)までに発しなければなりません。
- 議決権:原則として1株1議決権です。
9.3.2 取締役と取締役会
- 取締役:
- 意義:会社の業務執行を決定し、会社を代表する機関です。
- 職務:業務の決定、代表権の行使など。
- 善管注意義務や忠実義務を負い、これに違反した場合は会社や第三者に対して責任を負います。
- 取締役会:
- 意義:3人以上の取締役で構成され、会社の業務執行の意思決定を行う機関です。
- 役割:取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職など。
- 取締役会設置会社では、個々の取締役は原則として代表権を持ちません。
9.3.3 監査役と監査役会
- 監査役:
- 意義:取締役の職務執行を監査する機関です。
- 役割:会計監査(計算書類の監査)と業務監査(取締役の職務執行の適法性監査)を行います。
- 取締役からの独立性が求められます。
- 監査役会:
- 3人以上の監査役で構成され、その半数以上は社外監査役である必要があります。
- 監査役の職務執行に関する重要事項を決定します。
【ポイント】
会社の機関設計は、会社の規模や種類によって異なります。公開会社や大会社には、より厳格な機関設計(監査役会設置義務、会計監査人設置義務など)が求められます。
9.4 株式と株式の種類
9.4.1 株式の意義と種類株式
- 株式:
- 意義:株式会社の社員(株主)としての地位を構成する単位です。株式を取得することで、会社の株主となり、会社の利益分配や議決権などの権利を持つことができます。
- 原則:均等です。
- 種類株式:
- 意義:株主の権利の内容が、普通株式とは異なる株式です。定款で定めることで発行できます。
- 具体例:
- 剰余金配当優先株式:利益配当を普通株式より優先的に受けられる株式。
- 議決権制限株式:株主総会での議決権がない、または制限される株式。
- 取得請求権付株式:株主が会社に対して自己の株式の取得を請求できる株式。
- 取得条項付株式:会社が特定の事由により株主から株式を強制的に取得できる株式。
9.4.2 株券、株主名簿、株式譲渡
- 株券:
- 意義:株式の内容や株主の氏名などが記載された証券です。
- 原則:株券不発行が原則です。株券を発行する場合は定款にその旨を定める必要があります。
- 株主名簿:
- 意義:会社が作成する、株主の氏名、住所、所有株式数などを記載した帳簿です。
- 重要性:会社は、株主名簿に記載された者をもって株主として扱います。
- 株式譲渡:
- 原則:株式は自由に譲渡できます(株式譲渡自由の原則)。
- 対抗要件:株主名簿への記載(名義書換え)が、会社や第三者に対する対抗要件となります。
- 譲渡制限株式:定款で株式の譲渡を会社の承認にかからせる旨を定めることができます。これは、非公開会社で会社の構成員を限定したい場合に利用されます。
9.5 会社の計算:計算書類と株主総会承認
株式会社は、株主や債権者に対し、会社の財産状況や経営成績を報告する義務があります。
9.5.1 計算書類の種類と内容
事業年度ごとに、以下の計算書類を作成します。
- 貸借対照表(B/S):一定時点の会社の財政状態(資産、負債、純資産)を示します。
- 損益計算書(P/L):一定期間の会社の経営成績(収益、費用、利益)を示します。
- 株主資本等変動計算書:株主資本の変動状況を示します。
- 個別注記表:計算書類の記載だけでは不足する事項を補足します。
9.5.2 会計監査と株主総会承認
- 会計監査:
- 作成された計算書類は、監査役や会計監査人(大会社の場合)によって監査されます。
- 会計監査人は、会社の財務諸表が公正な会計慣行に従って作成されているかを独立した立場から監査します。
- 株主総会承認:
- 監査済みの計算書類は、定時株主総会に提出され、承認を受けなければなりません。
- これにより、株主は会社の財政状態や経営成績を把握し、経営の適法性をチェックすることができます。
9.5.3 利益配当
- 意義:会社が得た利益を、株主に対して分配することです。
- 原則:株主総会の決議によって行われます。
- 制限:会社の債権者保護のため、分配可能額の範囲内でしか配当できません。
9.6 会社の解散・清算
会社は、設立すれば永続するわけではありません。活動を終了する場合、解散し、法律に定められた清算手続を経て消滅します。
9.6.1 会社の解散事由
会社が解散する主な事由は以下の通りです。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散事由の発生
- 株主総会の決議:特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。
- 合併:会社が他の会社と合併し、消滅する場合。
- 破産手続開始の決定
- 解散命令または解散判決(裁判所による)
9.6.2 清算人
- 意義:会社が解散した場合、その後の清算事務を行う者を清算人といいます。
- 選任:原則として取締役が清算人となりますが、定款や株主総会の決議で他の者を選任することもできます。
- 登記:清算人の就任は登記が必要です。
9.6.3 清算業務の概要
清算業務は、解散した会社の残務処理を行い、最終的に会社を消滅させるための手続です。
- 現務の結了:未完の業務を終わらせます。
- 債権の取立て:会社が持つ債権を回収します。
- 債務の弁済:会社の債務を弁済します。この際、債権者に対し債権申出の催告を行い、債権者を保護します。
- 残余財産の分配:債務をすべて弁済した後、残った財産があれば、株主(出資者)に分配します。
- 清算結了の登記:清算事務がすべて完了したら、清算結了の登記を行い、会社は完全に消滅します。
【ポイント】
会社の解散と清算は、一連の法的プロセスです。特に債権者保護手続(債権申出の催告)は重要であり、これが適切に行われない場合、清算結了の効力が問題となることがあります。