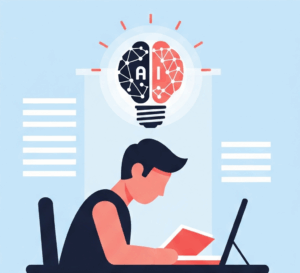
行政法は、行政書士試験の出題範囲の中でも最も配点が高く、最も重要な科目です。合格するためには、行政法を制することが不可欠と言われるほどです。この「総論」の章では、行政法全体の基本的な考え方や用語、制度の仕組みを体系的に学びます。ここでの基礎固めが、続く各論(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法)の理解を大きく助けます。
この章では、行政書士試験の最重要科目である「行政法」の全体像を学びます。行政法は、一言でいえば「行政を規律する法」です。国家権力のうち、「行政」が国民の生活にどのような形で関わり、どのようなルールに基づいて活動しているのかを理解することが、この章の目的です。複雑な概念も多いですが、一つずつ丁寧に紐解いていきましょう。
4.1 行政法とは何か?その特徴と基本原則
4.1.1 行政法の意義と行政の活動
行政法とは、行政組織、行政作用(活動)、行政救済など、行政に関する法規の総称です。特定の法律の名称ではなく、複数の法律(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法など)や判例、不文法を含む学問上の概念です。
では、そもそも「行政」とは何でしょうか?
国の活動を「立法」「行政」「司法」の三つに分ける三権分立の考え方から、行政は「立法でも司法でもない、国家の作用」と説明されます。
私たちの身近な行政活動の例は以下の通りです。
- 道路やダムの建設、水道・電気の供給
- 住民票の発行、印鑑証明書の交付
- 飲食店や建設業の営業許可、開発許可
- 所得税や固定資産税の賦課・徴収
- 災害時の救援活動や、生活保護の支給
4.1.2 行政と法の関係:行政における法治主義
憲法で学んだ「法治主義」は、特に行政法において重要な原則です。行政が国民の権利・自由を制限したり、義務を課したりする活動を行う際には、必ず法律に基づいて行われなければなりません。
この原則は、以下の3つの原則に分解して理解されます。
- 法律の法規創造力:
- 国会が制定した法律だけが、国民の権利・義務を定める規範(法規)を創り出すことができるという原則です。
- 行政機関は、原則として、法律の根拠なしに国民の権利・義務を定める法規(命令など)を創ることはできません。
- 法律優位の原則:
- 法律の下位にある行政のすべての活動は、法律に違反してはならないという原則です。
- 例:法律で認められていないにも関わらず、行政機関が特定の行為を禁止する命令を出すことはできません。
- 法律留保の原則:
- 行政が特定の活動を行う際には、必ず法律の根拠がなければならないという原則です。
- 特に、国民の権利・自由を制限したり、義務を課したりする「侵害行政」については、法律の根拠が必須とされています(侵害留保説)。
- 例:許可申請の却下、営業停止命令など。
【ポイント】
行政書士試験では、「行政活動には法律の根拠が必要か?」という視点が非常に重要です。特に、侵害行政については法律留保の原則が厳格に適用されることを覚えておきましょう。
4.2 行政組織法:行政機関の種類と権限
行政法は、行政の活動を規律するだけでなく、行政機関の組織や権限についても定めています。ここでは、行政の活動の主体となる様々な「行政機関」について学びます。
4.2.1 行政機関の分類
行政機関は、その権限や機能に応じて様々に分類されます。
- 行政庁(ぎょうせいちょう):
- 国の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ行政機関です。
- 例: 国務大臣(総理大臣、各省大臣)、都道府県知事、市町村長、税務署長など。
- 行政庁の行う行為(行政行為)は、国の意思として、直接国民に法律効果を及ぼします。
- 執行機関:
- 行政庁が決定した意思を単に執行(実行)する行政機関です。
- 行政庁の下位に位置し、自らの意思を外部に表示する権限はありません。
- 例: 警察官、消防官、税務職員など。
- 諮問機関・参与機関:
- 行政庁の決定を補助するため、意見を述べたり、審議に参加したりする行政機関です。
- 自ら意思を決定する権限はありません。
- 例: 審議会、審査会、有識者会議など。
- 補助機関:
- 行政庁や執行機関の職務遂行を補助する行政機関です。
- 例: 各省庁の事務次官、局長、課長、職員など。
- 行政委員会:
- 特定の行政分野において、強い独立性を持って権限を行使する合議制の機関です。
- 例: 公正取引委員会、人事院、国家公安委員会、教育委員会など。
- 委員会制をとることで、権限の行使が特定の人物の恣意に左右されることを防ぎ、専門性や中立性を確保します。
4.2.2 行政庁の権限
行政庁の権限には、主に以下の2種類があります。
- 法定受託事務:
- 国から地方公共団体に委ねられた事務です。
- 国の法律や政令に基づき、地方公共団体が国の機関として行います。
- 例: 旅券(パスポート)の発給、国政選挙の執行など。
- 地方公共団体の長(都道府県知事など)は、この事務の処理に関して、国の指揮監督を受けます。
- 自治事務:
- 地方公共団体が自主的に処理する事務です。
- 地方公共団体独自の条例や規則に基づき、地域住民のために行います。
- 例: 住民票の発行、消防事務、図書館の運営など。
- 国の指揮監督を受けず、自主性が尊重されます。
【ポイント】
行政機関の種類とそれぞれの権限・役割を理解することは、行政手続法や地方自治法を学ぶ上で非常に重要です。
4.3 行政作用法:行政行為の基本
行政行為とは、行政法総論の中心をなす最も重要な概念です。行政の活動のうち、特に国民の権利・義務に直接影響を及ぼす法的行為を指します。
4.3.1 行政行為の意義と種類
- 行政行為の意義:
- 行政庁が、法に基づいて、国民の具体的な権利・義務を直接設定したり、変更・消滅させたりする行為のことです。
- 例: 建築確認の許可、飲食店営業許可、運転免許の取消処分、所得税の賦課処分など。
- 行政行為の種類:
- 法律行為的行政行為:
- 行政庁の意思表示そのものに法的効果が発生する行政行為。
- 例:
- 命令的行為(許可、特許、免許など): 許可(特定人が特定の行為を自由に行うことを認めること)、特許(特定の権利や特権を与えること)、免許(特定の資格を付与すること)など。
- 形成行為(認可、代理など): 認可(第三者の法律行為を有効にすること)、代理(行政庁が他人の代わりに行為を行うこと)など。
- 準法律行為的行政行為:
- 行政庁の意思表示ではなく、法律が特定の効果を定めている行政行為。
- 例: 確認、公証、通知、受理など。
- 法律行為的行政行為:
4.3.2 行政行為の効力
行政行為には、私人の行為にはない、いくつかの特別な効力があります。
- 公定力(こうていりょく):
- 行政行為に違法な点があったとしても、権限のある行政庁や裁判所によって取り消されるまで、有効なものとして扱われる効力です。
- 【ポイント】 違法な行政行為であっても、私人が勝手に無効だと主張して従わないことはできません。国民は、行政不服審査法や行政事件訴訟法に基づき、正式な手続きで取り消しを求める必要があります。
- 不可争力(ふかそうりょく):
- 行政行為の取り消しを求めることができる出訴期間(原則として処分を知ってから6ヶ月)が経過すると、もはやその行為の効力を争うことができなくなる効力です。
- 【ポイント】 国民の救済は一定の期間内に限られる、という考え方に基づいています。
- 不可変更力(ふかへんこうりょく):
- 行政行為を行った行政庁自身が、一度行った行為を一方的に変更したり、取り消したりすることができなくなる効力です。
- 【ポイント】 裁判の判決など、特定の行為にのみ生じる効力です。
- 強制力(きょうせいりょく):
- 行政行為で命じられた義務が履行されない場合に、行政が自ら強制的にその義務を履行させる(代執行など)ことができる効力です。
4.3.3 行政行為の附款(ふかん)
- 意義: 行政庁が、行政行為の主たる内容に付加して定める従たる意思表示のことです。
- 例: 飲食店営業許可(主たる内容)に、「午前0時以降は営業してはならない」という条件を付けること。
- 種類:
- 条件: 将来の不確実な事実の発生に、行政行為の効力の発生・消滅を依存させるもの。
- 期限: 将来の確実な事実の発生に、行政行為の効力の発生・消滅を依存させるもの。
- 負担: 行政行為の相手方に、別の義務を課すもの。
- 撤回権の留保: 行政庁が将来、一方的にその行政行為を撤回する権利を留保すること。
【ポイント】
附款は、行政行為の主たる内容と密接な関連性がなければならず、濫用は許されません。
4.3.4 行政行為の違法性・無効
行政行為に法律違反がある場合でも、その違法性の程度によって効力が異なります。
- 取消しうる違法:
- 公定力があるため、権限ある機関によって取り消されるまで有効なものとして扱われる違法性です。
- 【ポイント】 軽微な法律違反や、手続き上の不備など、法律違反が重大でない場合。
- 無効(当然無効):
- 法律違反が著しく重大で、誰が見てもその行政行為が法律上存在しないと認められる場合です。
- この場合、公定力は働かず、最初から無効とされます。
- 【ポイント】
- 無効の要件: 「重大かつ明白な瑕疵」があること。
- 例: 存在しない法律を根拠に行政行為を行った場合、処分権限のない機関が処分を行った場合など。
4.4 その他の行政作用:行政指導・行政計画・行政契約
行政は、行政行為だけでなく、様々な手段で活動しています。これらの手段は、行政行為とは異なる法的性質を持ち、行政法総論では重要なテーマです。
4.4.1 行政指導(ぎょうせいしどう)
- 意義: 行政機関が、相手方(私人)の任意の協力を求めることで、特定の行政目的を実現しようとする行為です。
- 特徴:
- 非権力性: 相手方の同意を前提とし、法的な強制力は一切ありません。
- 【ポイント】 相手方は行政指導に従う義務はなく、従わなくても不利益な扱いを受けることはありません(行政手続法第32条)。
- 法的問題点:
- 行政指導が、事実上強制力を持つように行われる場合(例:業者に行政指導に従わないと不利益な扱いをすると示唆するなど)、法律の根拠がないにも関わらず、国民の権利・自由を不当に制限する「脱法行為」となる危険性があります。
- 行政手続法は、行政指導が濫用されないよう、その手続きを定めています。
4.4.2 行政計画(ぎょうせいけいかく)
- 意義: 行政機関が、特定の行政目的を達成するために、将来の目標や方針、事業計画などを定めることです。
- 例: 都市計画、交通計画、環境保全計画など。
- 法的性質:
- 原則: 国民の権利・義務に直接的な影響を及ぼさないため、法規性を持たないとされます。
- 例外: 特定の行政計画が、国民の法的地位に直接的な影響を与える場合には、例外的に法律上の行為として訴訟の対象となる場合があります。
- 重要判例(行政計画):
- 都市計画法に基づき建築を制限する条例を定めた行為:
- 判旨: 行政計画は通常は法的性質を持たないが、その計画が国民の権利義務に直接的な変動を生じさせる場合には、行政訴訟の対象となるとしました(最高裁の判例)。
- 都市計画法に基づき建築を制限する条例を定めた行為:
4.4.3 行政契約(ぎょうせいけいやく)
- 意義: 行政主体と私人が、対等な立場で特定の目的のために締結する契約です。
- 特徴:
- 対等な立場: 公権力の行使ではなく、私法上の契約と同じように、双方が合意して成立します。
- 例:
- 私法上の契約: 行政庁が備品を購入する契約、公務員を雇用する契約など。
- 公法上の契約: 学術研究の委託契約、道路整備のための共同開発契約など。
- 【ポイント】 行政契約の有効性や履行に関する紛争は、原則として民事訴訟で争われます。
4.5 情報公開法・個人情報保護法
行政の透明性を確保し、国民の行政活動への監視を可能にするための重要な法律です。
4.5.1 行政機関情報公開法
- 意義: 行政機関が保有する行政文書を、国民からの請求に応じて公開することを定めた法律です。
- 目的: 国民に「知る権利」を保障し、行政の活動を監視することで、国民に行政の公正な運営を確保する責務を負わせることを目的とします(行政手続法第1条)。
- 公開請求の原則:
- 誰でも、行政機関に対して、行政文書の公開を請求できます。
- 公開することが義務であり、非公開とできるのは、法律に定められた特定の非公開情報(不開示情報)に該当する場合のみです。
- 不開示情報の例:
- 個人のプライバシーに関する情報。
- 法人の正当な利益を害する情報。
- 公開することで公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼす情報。
- 審議、検討、協議に関する情報で、公開することで意思決定に著しい支障が生じるおそれがある情報。
- 犯罪の予防や捜査、裁判の遂行に支障を及ぼす情報。
- 不服申立て・訴訟:
- 公開請求に対して非公開決定がなされた場合、国民は行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起できます。
4.5.2 個人情報保護法
- 意義: 行政機関が保有する個人情報について、その適正な取り扱いを定めた法律です。
- 目的: 個人の権利利益を保護し、行政の適正な運営に資することを目的とします。
- 重要ポイント:
- 利用目的の特定: 個人情報を取得する際には、利用目的をできる限り特定しなければなりません。
- 本人同意の原則: 原則として、本人の同意なしに個人情報を目的外で利用したり、第三者に提供したりすることはできません。
- 開示、訂正、利用停止等の請求権: 本人は、自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止などを求めることができます。
4.6 行政立法と行政計画
行政が定めるルールには、国民の権利・義務に直接関わるものと、そうでないものがあります。
4.6.1 行政立法(ぎょうせいいっぽう)
- 意義: 行政機関が定める、法規としての性質を持つルール(命令、規則など)のことです。
- 種類:
- 法規命令:
- 法規性を持ち、国民の権利・義務に直接的な影響を及ぼす命令です。
- 例: 法律を具体化するための施行令・施行規則。
- 【ポイント】
- 委任命令: 法律の委任を受けて、法律の内容を具体化するために制定される命令。
- 執行命令: 法律の執行に必要な手続きなどを定める命令。
- 行政規則:
- 行政機関内部の組織や活動を規律するもので、法規性を持ちません。
- 国民の権利・義務に直接影響を及ぼすことはありません。
- 例: 訓令、通達、要綱など。
- 法規命令:
【ひっかけポイント】
- 行政立法のうち、法規命令は裁判の対象となりますが、行政規則は原則として裁判の対象となりません。
- 判例は、行政規則であっても、それが国民の法的地位に直接影響を与える場合には、例外的に裁判の対象となると判断することがあります。
4.7 行政上の強制執行・即時強制
行政上の義務が履行されない場合に、行政がその義務を強制的に履行させるための手段です。
4.7.1 行政上の強制執行
- 意義: 義務が履行されない場合に、将来に向かって強制的にその義務を履行させることです。
- 種類:
- 代執行(だいしっこう):
- 義務者がすべき行為をしない場合に、行政が代わりに行い、その費用を義務者から徴収することです。
- 要件:
- 法律上の代替的作為義務があること。
- その義務が履行されないこと。
- 他に代執行の手段がないこと。
- 文書による戒告、代執行令書の交付などの手続きを経ること。
- 執行罰(しっこうばつ):
- 義務者に過料(罰金)を科すことで、心理的な圧力をかけ、義務の履行を促すことです。
- 法律に根拠がある場合にのみ許されます。
- 直接強制:
- 義務者の身体や財産に直接、実力を行使して義務を履行させることです。
- 原則として法律の根拠がないと行えません。
- 代執行(だいしっこう):
4.7.2 即時強制(そくじきょうせい)
- 意義: 義務の履行を待っていては、公共の安全に重大な危険が及ぶような緊急事態において、即座に、直接、実力を行使して危険を排除することです。
- 【ポイント】
- 強制執行と異なり、義務の不履行を前提としません。
- 例:
- 火事の現場で、消防隊員が延焼を防ぐために隣接する建物を破壊すること。
- 伝染病の感染拡大を防ぐため、患者を強制的に隔離すること。
- 要件:
- 差し迫った危険があること。
- 他に代替手段がないこと。
- 法律の根拠があること。
4.8 行政上の義務履行確保:行政調査・行政罰
行政は、国民の義務履行を確保するため、様々な手段を講じます。
4.8.1 行政調査(ぎょうせいちょうさ)
- 意義: 行政目的を達成するために、行政機関が国民の活動や財産、状況などについて事実を明らかにするための情報収集活動です。
- 特徴:
- 任意調査: 相手方の同意を得て行われる調査。原則として拒否できます。
- 強制調査: 相手方の同意なしに、強制的に行われる調査。法律に根拠がある場合にのみ行えます。
- 例:
- 税務調査(国税通則法に基づく強制調査)
- 犯罪捜査(刑事訴訟法に基づく強制捜査)
- 飲食店の衛生状態の調査(食品衛生法に基づく任意調査)
4.8.2 行政罰(ぎょうせいばつ)
- 意義: 行政上の義務違反に対する制裁として、行政が科す罰則のことです。
- 種類:
- 行政刑罰:
- 行政上の義務違反に対して、刑法に定められた「懲役」「禁錮」「罰金」などの刑罰を科すものです。
- 法律(個別の法律や行政罰法など)に規定されている場合にのみ、刑事訴訟の手続きを経て、裁判所の判決によって科されます。
- 例: 無許可で飲食店を営業した場合に、罰金を科されること。
- 秩序罰(ちつじょばつ):
- 法律や条例で定められた秩序違反に対して、「過料」を科すものです。
- 刑罰ではないため、前科はつきません。
- 【ポイント】 裁判所の決定によって科されるもの(例:訴訟手続きを妨害した場合の過料)と、行政庁が直接科すもの(例:地方自治法に基づく過料)があります。
- 行政刑罰:
【整理】
- 行政刑罰: 刑罰。裁判所が科す。
- 秩序罰: 罰則(刑罰ではない)。裁判所または行政庁が科す。